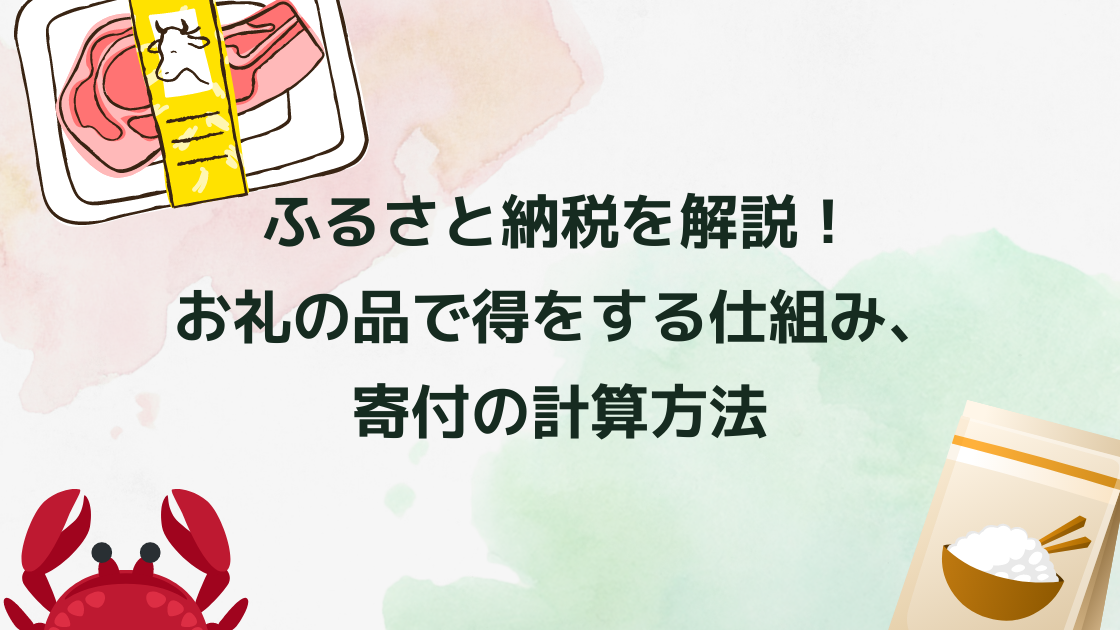貯金できない人へ贈る 3つの貯金のアドバイス
 収入が少ないわけじゃないのになぜかお金が貯まらないという人も実は多いです。
収入が少ないわけじゃないのになぜかお金が貯まらないという人も実は多いです。
ある調査では年収1000万円以上の世帯でも30%の世帯が日常的にカードローンを使っているという調査があります。
つまり、収入が多ければ貯金できるというのは間違いで、意識的に貯金をしなければ収入が多くても貯金できないのです。一方で収入が低くても毎年しっかりと貯金残高を積み上げている方もいらっしゃいます。
今回はそんな、貯金ができないという方にお勧めの3つの貯金のためにおさえておきたいポイントについてまとめていきます。基本は「目標設定」「天引き」「支出削減」の3つです。
なかなか貯金ができないという人は、貯金のやり方がまずいケースが多いです。貯金ができるシステムを作っているか?ということなのです。
貯金できないのは貯め方が間違っている。強制的に貯金するシステムを作るべき
ある程度収入があるはずなのに、全く貯金ができていない。そう嘆く方は少なくないです。一方で収入はさほど高くない方でも毎年、収入のかなりの割合を貯金できている人がいます。
この違いは何なのでしょうか?
冒頭で、収入が多くても貯金が全くできない人がいると書きました。有名なお話に「パーキンソンの法則」というものがあります。これの一つに、“支出の金額は収入の額に達するまで膨張する”という一言があります。
貯金ができないというの人は、なんとなく貯金をしようとは思っている人が多いです。
貯金がをするのであれば強制的に貯金ができるシステムを作るべきです。
貯金できている人
→毎月の貯金する金額を決めてから生活している
貯金できない人
→毎月の生活で余ったお金を貯金する
この違いだけです。貯金できないと嘆いているかたはここを改めるだけで大きく変わってくることは間違いありません。
じゃあ、どうすればいいのか?というと以下の3つの方法をお勧めします。
- 目標から逆算して貯金をする
- 天引き・先取で貯金をする
- 不足分は支出の削減でカバーする
この3つのアドバイスを実行に移せば、必ず貯金できるはずです。
目標から逆算して貯金のための第一歩を踏み出す
まずは、目標をたてましょう。漠然と貯金を始めるよりも、1年で100万円貯金するというように目標を立てるほうが、貯金対するモチベーションも高めやすいです。
100万円の貯金なら月額8万3334円が基準となりますね。
いやいや、そんな金額は貯金できないよ……という否定から入るのではなく、そのためにどうすればいいのかを考えていきましょう。
もちろん、手取り15万円で8.3万円を毎月貯金というのは現実的ではありませんので、現実的な目標を立てるようにしましょう。
目標としては手取りの20%程度を目標としたいところです。
天引き・先取で貯金をする
一番効果的な方法はこの天引き貯金・先取り貯金をするという方法です。
先ほど書いたように貯金できている人は「あらかじめ貯金する金額を決めている」のです。なので、貯金できない人はこれを真似てしまいましょう。
一番簡単なのは収入が入ってくる段階で天引き、あるいはそれに近い形で強制的に貯金をしてしまうという方法になります。
もっとも基本的といえるのが、“積立貯金”のような金融サービスを使えばいいのですが、それ以外にも様々なサービスがあります。
[bloglink url=”https://money-lifehack.com/bank/1631″]
月額8.3万円を天引き、先取りで貯金をするようにすれば、1年後には100万円が貯まっています。
勤務先の貯蓄制度を利用する
勤務先で「財形貯蓄」や「自社株積立(従業員持ち株会)」のような方法があるのであればこうした方法を活用しましょう。給料からあらかじめ天引きされるので強制的に貯金されます。
なお、財形については預金となるのでリスクはありません。会社によってはもっと有利な金利で預金ができる社内預金などの制度がある会社もあるかもしれません。うまく使っていきましょう。
[bloglink url=”https://money-lifehack.com/working/4846″]
[bloglink url=”https://money-lifehack.com/working/9675″]
一方で従業員持ち株会は自社の株式を購入することになるので運用リスク(株価変動のリスク)があります。また、収入と資産の両方を会社(勤務先)にゆだねることになります。従業員持ち株会の割合を増やしすぎるのも考えものなので、割合は調整しましょう。
[bloglink url=”https://money-lifehack.com/asset-management/1868″]
銀行や証券会社の積立関連のサービスを利用する
勤務先の天引きが使えない(制度がない)という場合でも、民間の金融機関のサービスを利用すればほぼ同じことが可能です。
続いては銀行や証券会社で提供している積立関連のサービスを使う方法があります。代表的な物が「積立貯金(積立定期預金)」でしょう。金利はほぼ期待できないのが現状となっていますが、指定日時に自動引き落としとなるので、給料日に指定しておけば自動的に貯金ができます。
[bloglink url=”https://money-lifehack.com/bank/1631″]
また、最近ではネット銀行などを中心に自動振替サービスなどもあります。たとえば、「銀行の自動入金サービス」でも紹介しているような仕組みを使えば、給料振込から「生活費用」「貯蓄用」「投資用」などの資金を振り分けていくのが簡単になります。
住信SBIネット銀行は貯金用にも資産運用にも活用できる銀行なので、ぜひ口座をお持ちでない方は作っておきましょう。
[bloglink url=”https://money-lifehack.com/bank/12352″]
老後の資金なら引出ができないiDeCo(個人型確定拠出年金)などに振り替えるのもOK
貯金の目的が老後のためというのであれば年金関連のサービスもお勧めです。2017年1月からは個人型確定拠出年金(iDeCo)への加入条件が緩和されほぼすべての人が加入できるようになりました。
掛け金は全額所得控除となるので、節税効果もきわめて高い制度となっています。老後が不安でそれに備えていきたいというのであれば最適です。
[bloglink url=”https://money-lifehack.com/asset-management/1348″]
ただし、iDeCo(イデコ)の場合、預けたお金は老後(60歳)までは引き出すことができません。貯金ゼロの状態から引出し不能な形にしておくのは、万が一の生活防衛のことを考えると好ましくありません。
貯金が少ないうちは、同じ非課税運用でも引き出しも可能な「NISA」や「つみたてNISA」などを利用するほうがいいかもしれません。
[bloglink url=”https://money-lifehack.com/asset-management/1835″]
不足分は支出の削減でカバーする
貯金を先取りしたあとは、その残ったお金で生活していく必要があります。結局お金が足りずに貯金を崩したり、キャッシングやカードローンでお金を借りるというのは本末転倒です。
いくら先取(天引き)で貯金をしたとしても、これまでと同じような支払いを続けていたら、当然不足するはずです。
そうならないためにも、最初に立てた目標を達成するために支出削減にも取り組みましょう。特に、高収入なのに、
家計の固定費を削るのは最優先
家計改善において最も効果的で、持続性が高いのが固定費の節約です。
[bloglink url=”https://money-lifehack.com/savings/738″]
- 家賃・駐車場代
- 保険料(自動車保険・生命保険)
- インターネット回線料金
- 携帯電話料金
- 新聞代
- ガス代・電気代
- 習い事や趣味の費用
こういった費用ですね。毎月ほぼ固定で必要になるお金です。いずれも見直しの余地がある方は多いと思います。
たとえば、家賃であればもっと安いところに引っ越しをするという方法もありますし、場合によっては「家賃交渉」をすることだって考えられます。
自動車保険は毎年見直しをすることで節約可能ですし、生命保険などはもしかしたら必要以上の保険に入っているかもしれません。
場合によっては自動車は所有するのではなく、カーシェアなどに切り替えて必要な時に支払うことで固定費を大きく節約できるでしょう。
携帯電話料金はMVNO(格安SIM)などに切り替えることで節約できますし、ガス代や電気代も現在は自由化されているので、地域や家族構成などによっても違いますが、切り替えで節約できるケースもあります。
新聞代も切れとは言いませんが、最近はネット系のサービスで代替できるサービスもあります。特に一部の証券会社が提供している「日経テレコン」などは新聞をほぼ代替できるようになっています。
こんな風に、色々な方法がありますよね。固定費節約のいいところは、見直しをするのは少し面倒に思うかもしれませんが、一度実行すれば、翌月からは何もしなくても削減効果が持続することです。
変動費は家計簿アプリを使って収支状況を見える化する
家計簿をつけるというのは、支出を管理して次に生かしていく(問題点を把握する)上でとても大切です。多くの方が家計簿をつけることは大切という認識は持っているかと思います。
その一方で家計簿をつけるというのはかなり手間です。実際に家計簿についての意識調査では男性の5割、女性の7割が家計簿をつけたけど挫折した経験をお持ちということです。
そんな家計簿ですが、近年ではペーパータイプではなく、スマートフォンのアプリを使ったタイプが主流化しつつあります。しかも、クレジットカードや銀行口座との自動連携などによって、家計簿をつける手間もずいぶんと簡略されています。
[bloglink url=”https://money-lifehack.com/savings/5741″]
上記で紹介しているように、スマホアプリの中には家計簿アプリのようなものがあり、クレジットカードなどを登録しておけば、ほぼ入力まで自動化できるので大変便利になっています。
目標を立て、システム的に貯金をすすめていこう
長々となりましたが、今回紹介した方法はすべてをキッチリとやらないとダメということはありません。多少緩くやっても大丈夫です。
何にしても、行動を起こすとき、第一歩を踏み出すことが大切です。
[bloglink url=”https://money-lifehack.com/education/1615″]
特に、貯金を始めるというような行動を必要とするときは、やろうと思っても、そんな色々しないとだめなら、また今度でいいか。という気持ちになりやすいです。
これは、現状維持バイアスといって「行動経済学」という分野で研究されているものです。
この記事を読んでムクムクとわいてきたであろう、「まあ、でも今すぐ必要ってわけじゃないだろう」という気持ちは現状維持バイアスによるものです。
貯金用の銀行口座を作るでもいいですし、固定費見直しに動くでもいいです。まずは行動しましょう
以上、なかなか貯金ができない家計へ贈る 3つの貯金ポイントでした。
今、一番おすすめのモバイル回線は「楽天モバイル」です。
今は『楽天モバイル』が最強。楽天リンクを使えば通話かけ放題だし、パケットも使い放題で月々3,168円。データ通信をあんまり使わない人は1,078円で回線を維持できます。
さらに、家族と一緒なら110円OFF。
今なら三木谷社長からの特別リンクから回線を作ると、他社からMNPで14,000ポイント。新規契約なら11,000ポイントもらえるぶっ壊れキャンペーン中。