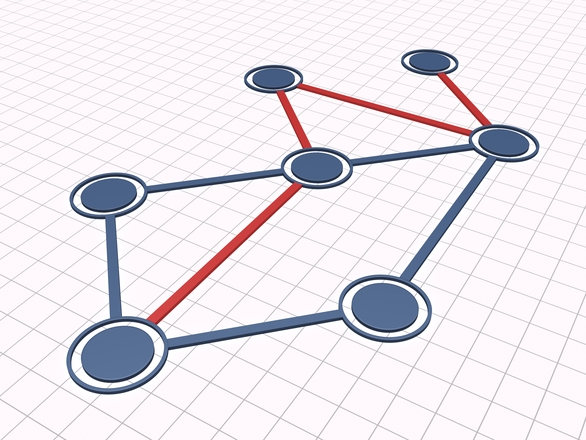つみたてNISAが2018年スタート。積立NISAのメリット、デメリット。一般NISAとの比較
 2018年1月から少額投資非課税制度(NISA)に3番目の制度が加わります。それがつみたてNISAと呼ばれるものです。非課税の限度額が年40万円と一般NISAの1/3ですが、非課税期間が20年(一般NISAは5年)と4倍の期間非課税で運用することができます。
2018年1月から少額投資非課税制度(NISA)に3番目の制度が加わります。それがつみたてNISAと呼ばれるものです。非課税の限度額が年40万円と一般NISAの1/3ですが、非課税期間が20年(一般NISAは5年)と4倍の期間非課税で運用することができます。
NISA(小額投資非課税制度)はこのつみたてNISAが加わることで3種類のNISAが存在することになります。未成年向けのジュニアNISAを別とすると、20歳以上の方は「一般NISA」と「つみたてNISA」のどちらかを選択する必要があります。
今回はそんな、つみたてNISAの基本的な特徴やメリット、デメリット。一般NISAと積立NISAはどちらを選ぶべきかについての比較をしていきます。
NISA(小額投資非課税制度)のまとめ
まず、NISA(少額投資非課税制度)についてまとめます。
NISAは年間投資額上限が120万円でその枠内で購入した株や投資信託の運用益や売却益が最長5年間非課税となる制度です。
[bloglink url=”https://money-lifehack.com/asset-management/5554″]
また、NISAは20歳以上向けの制度ですが、未成年向けの制度としてジュニアNISAがあります。こちらは一般NISAと違って出金制限があるなどの制限がかかっています。
[bloglink url=”https://money-lifehack.com/asset-management/3211″]
2017年7月現在ではこのNISAは2種類が存在していますが、これに2018年1月より積み立て投資による長期資産運用を目的とする「つみたてNISA」が登場することになります。
つみたてNISA(積立NISA)とは何か?
2018年1月導入のつみたてNISAは、一般NISAと選択制で利用できる少額投資非課税制度です。
年間の投資可能額が通常の1/3(40万円まで)である一方、配当金(分配金)や売買益が非課税となる期間が通常の4倍となっています。
- 2018年1月より開始 (募集は「SBI証券」「楽天証券」でスタート)
- 非課税期間は最長20年
- 非課税投資枠(年間投資上限)は40万円
- つみたてNISAで買えるのは一定の条件を満たした投資信託のみ
- 買い付けは積立である必要がある
このように従来のNISAとは非課税期間や非課税枠以外にも違いがあります。
つみたてNISAのメリットは何といっても長期の非課税期間
つみたてNISAの最大のメリットは「長期の積み立て投資の運用益が非課税になること」です。
[bloglink url=”https://money-lifehack.com/tax/9033″]
上記の記事でも説明していますが、「税金」というのは100%確実に発生する運用益を強制的にマイナスにしてしまう存在です。日本の投資の税金は20.315%(復興特別所得税を含む)となっていますので、仮に毎年課税されるとするとその分だけ運用益を落とすことになります。
以下は年利別に20年間を課税口座(通常口座)、非課税口座(つみたてNISA)で運用した場合、100万円がいくらになるかを表にしたものです。
| 2% | 3% | 4% | 5% | 6% | |
|---|---|---|---|---|---|
| 通常口座 | 137万円 | 160万円 | 187万円 | 218万円 | 254万円 |
| 積立NISA | 148万円 | 180万円 | 219万円 | 265万円 | 320万円 |
同じリスクをとって運用したのにかなりの差が生じることがわかっていただけるかと思います。これが税金の力と複利効果が混ざったものなんです。
[bloglink url=”https://money-lifehack.com/asset-management/5003″]
一般NISAと積立NISAの比較
この積立NISAと一般NISAはどちらかを選択して一方のみが使えるという制度になる予定です。一年あたりの投資上限額は低いけど非課税期間がながい積立NISAか、一年あたりの投資上限額が高いNISAかを選択する必要があるわけです。
それでは一般NISA、積み立てNISA、ジュニアNISAについてそれぞれを比較してみましょう。ただし、ジュニアNISAについては、年齢という部分で完全に区切られているので使い分けはできませんね。
一般NISAとつみたてNISAはどちらかを選択することになります。
| 一般NISA | つみたてNISA | ジュニアNISA | |
|---|---|---|---|
| 年齢 | 20歳以上 | 20歳以上 | 0歳~19歳 |
| 年間非課税投資上限額 | 120万円 | 40万円 | 80万円 |
| 非課税期間 | 5年 | 20年 | 5年 |
| 総非課税金額 | 600万円 (120万円×5年) |
800万円 (40万円×20年) |
400万円 (80万円×5年) |
| 投資対象 | 株・投資信託 | 一部の投資信託 | 株・投資信託 |
| 払い出し制限 | なし | なし | あり |
| 口座名義 | 本人 | 本人 | 子 |
つみたてNISAの投資可能な投資信託
補足が必要であろう部分として、一般NISAは投資対象は株や投資信託で自由に選ぶことができます。
一方で、つみたてNISAについては一定の基準のもとで選別された限られたファンドが対象になります。
事前報道によると投資可能なのは50本程度になる見込みなのだとか。
限定する理由は「長期投資に資するものである必要がある」ということです。
[bloglink url=”https://money-lifehack.com/diary/10166″]
こちらでも取り上げましたが、日本で販売されている投資信託の多くは手数料が高い、分配型で長期投資に適していないなどの理由で長期投資に向かないファンドが多いです。
こうした投資信託をお上が選別するということがいいか悪いかは別として、コストの高いファンドを最初から除外してくれているというのはある意味、投資初心者の方にはよいかもしれません。
どっちのNISAが自分に向いている?
一年あたりの上限枠は一般NISAのほうが大きいですが、非課税期間が長いため長期保有する前提があるのであれば、つみたてNISAのほうが総額としては大きくなります。
一般NISAがお勧めな人
- 投資信託ではなく個別株式での投資をしたい人
- 投資する投資信託は自分で選びたい人
- 投資できる資金が豊富な人
[bloglink url=”https://money-lifehack.com/asset-management/1761″]
積立NISAがお勧めな人
- 毎月の積立投資をコツコツとやっていきたいと考えている人
- 投資対象を選別したり選ぶのが面倒な人
[bloglink url=”https://money-lifehack.com/asset-management/12744″]
こんな感じでしょうか。
一般NISAとつみたてNISAに変更は可能
一般NISAとつみたてNISAは制度的には同じで、それぞれ変更(切り替え)することができます。一応1年単位での変更が可能なので、手続き上面倒ですが、今年の分は「つみたてNISA」、来年の分は「一般NISA」といったように変更することは可能です。
個人型確定拠出年金(iDeCo)とは併用可能
つみたてNISAと同様に積立投資かつ節税効果の高い「個人型確定拠出年金(iDeCo)」という制度もあります。どちらも同じように運用益が非課税となる制度で、毎月積み立てていくといった共通点も多いです。
この制度とつみたてNISAは併用が可能なので、それぞれの特色を抑えたうえで、使い分けをするのがおすすめです。詳しい制度の比較は下記の記事をご覧ください。
[bloglink url=”https://money-lifehack.com/tax/12746″]
以上、積立NISAを紹介しました。この記事は積立NISAについての情報が出次第アップデートしていきます。
今、一番おすすめのモバイル回線は「楽天モバイル」です。
今は『楽天モバイル』が最強。楽天リンクを使えば通話かけ放題だし、パケットも使い放題で月々3,168円。データ通信をあんまり使わない人は1,078円で回線を維持できます。
さらに、家族と一緒なら110円OFF。
今なら三木谷社長からの特別リンクから回線を作ると、他社からMNPで14,000ポイント。新規契約なら11,000ポイントもらえるぶっ壊れキャンペーン中。