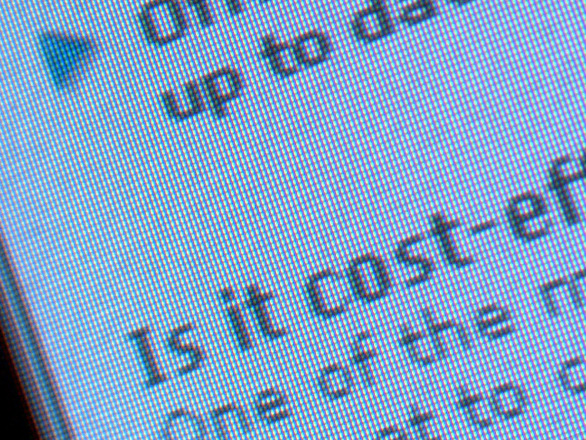投資信託の保有ポイント制度でネット証券を比較
 ネット証券の中には投資信託を保有することでポイントが付与するところが数社あります。これらのサービスを利用すれば、投資信託の保有コストである信託報酬の一部を実質的に値引きしてくれることになります。最近ではローコストで運用可能な投資信託(インデックスファンド)も増えていますが、ネット証券のこうしたポイントサービスを活用することで、さらに得をすることができます。
ネット証券の中には投資信託を保有することでポイントが付与するところが数社あります。これらのサービスを利用すれば、投資信託の保有コストである信託報酬の一部を実質的に値引きしてくれることになります。最近ではローコストで運用可能な投資信託(インデックスファンド)も増えていますが、ネット証券のこうしたポイントサービスを活用することで、さらに得をすることができます。
今回は2021年12月時点で投信ポイントサービスを提供している「SBI証券」「auカブコム証券」「楽天証券」「マネックス証券」「松井証券」のそれぞれのサービス内容の比較や対象外ファンドなどについてわかりやすく紹介、比較していきます。
まずは投資信託の手数料(コスト)の仕組みを知ろう
投資信託には大きく「販売手数料(購入時にかかる手数料)」と「信託報酬(投資信託の保有する期間中かかる運用経費)」「信託財産留保額(投資信託を解約するときの手数料)」の三つがあります。
| 手数料の特徴 | |
|---|---|
| 販売手数料 | 販売会社により異なります。同じファンドでも銀行では手数料が2%かかるけど、ネット証券なら無料というものも多いです。 |
| 信託報酬 | どの証券会社で買っても共通です。 |
| 信託財産留保額 | どの証券会社で買っても共通です。 |
こちらで紹介しているように、販売手数料については投資信託を売っている証券会社によっても差があります。「投資信託はどこで買うのがおすすめ?銀行・証券会社・ネットバンク・ネット証券を比較」などで銀行や証券会社の窓口でファンドを買うべきではないと書いているのは手数料が高いからというのが理由の一つです。
その一方で、投資信託で中長期の資産運用を考えたときに、コストとして大きなものは「信託報酬」という管理手数料です。こちらはファンドごとに定められており、どの証券会社で購入しても同じです。
ファンドによって差があるので「投資信託の選び方と資産配分(アセットアロケーション)の考え方」で紹介しているように、投資をするときは信託報酬の安いものを選ぶことが重要です。実際にインデックスファンドでコストの安いものについては「日経平均株価に連動するおすすめの投資信託(インデックスファンド)」などでも紹介しています。
投信ポイントサービスは事実上の信託報酬の割り戻しになる
さて、そんな信託報酬ですが、安いファンドを探すというのももちろん大切なのですが、投信ポイントサービスを活用するという方法も検討してはいかがでしょうか。
投信ポイントサービスとは、提供している証券会社(ネット証券)によって差があるものの、投資信託の保有残高に応じて残高の一定割合をポイントとしてキックバックしてくれる制度です。
たとえば、「SBI証券の投信マイレージサービスのメリット、デメリット」でも紹介したSBI証券は投信マイレージとして投資信託として預けている金額(残高)の0.1%~0.2%をSBIポイントとして還元してくれます。
これは言い換えれば、0.1%~0.2%分の信託報酬がキックバックされるということになるわけです。たとえ0.1%という数字でも投資金額が1000万円なら年間で1万円も差が出る計算になるわけで決して馬鹿にはできません。
ネット証券各社の投信ポイントサービスの比較
| ネット証券 | 投信ポイントの特徴 |
|---|---|
| SBI証券 | 投信マイレージプログラムとして、保有残高の0.1~0.2%分がSBIポイントとして還元されます。 現在はSBIポイントではなく、ポイント連携することでTポイントまたは、Pontaポイントに交換することもできるようになっています。最低利用額の観点からもポイント連携しておくのをおすすめします。<低コストファンド> ※信託報酬が極端に安いファンドは例外ファンドとして0.01%~0.05%のポイント還元となります。 |
| auカブコム証券 | 100万円ごとに毎月1ポイントがポイントバックされます。率にすれば0.12~0.24%とSBI証券よりもバック率は高いです。ただし、換金制限とポイント有効期限の関係から最低でも300万円以上の投資をしていないとキャッシュバックの対象になりません。
<低コストファンド> |
| 楽天証券 | 投資信託によって0.036%~0.12%と付与に幅があります。2022年4月以降はポイント付与の方式がし定額到達時の1回こっきりに変更される予定です。 |
| マネックス証券 | 月の平均投資信託残高に応じてのマネックスポイントがたまります。 0.03%(指定銘柄) 0.08%(通常) マネックスポイントはdポイントやTポイントなどと交換できます。 |
| 松井証券 | 各投資信託の信託報酬のうち、松井証券の受取分として0.3%を設定し、それを超えて金額を全額キャッシュバック。0%~0.7%程度。 |
せっかくなら還元率が高いところを利用したいところですよね。でも、説明にも書いていますが、いくつか注意点があります。
ポイント対象外ファンドがある
注意点として大きいのはこの「対象外ファンド」の存在です。
特に、上記の証券会社の投信ポイントサービスのうち「松井証券」は対象外(あるいは実質的に対象外)のファンドが数多く存在する仕組みになっています。信託報酬(保有コスト)の高いファンドしかそもそも還元対象ではないのです。理由は信託報酬の額が小さすぎて、ポイント還元すると逆に証券会社側が赤字になってしまうということがあげらるでしょう。ただ、ポイント目当てにあえて手数料が高いファンドを買うというのも無駄ですよね。
見た目では、松井証券の最大0.7%、auカブコム証券の最大0.24%還元が大きく見えますが、実際のところだと還元があまり期待できなかったりします。
SBI証券やマネックス証券については、ローコストのファンドでも投信ポイントが付与されます。そのため、投資信託を保有するならSBI証券かマネックス証券のどちらかということになりそうです。
SBI証券とマネックス証券、楽天証券ならどれがお得?
両社のポイント付与率は下記のようになっています。
| SBI証券 | マネックス証券 | 楽天証券 | |
|---|---|---|---|
| 基本ポイント付与率 | 0.1%~0.2% | 0.08% | 0.036%~0.12% |
| 制限対象のファンド | 0.01%~0.05% | 0.03%(一部ファンドは0%) |
私は投資信託の保有は原則としてコストの安いインデックスファンドであるべきだと考えています。
eMAXIS Slimや<購入・換金手数料なし>シリーズ、たわらノーロードシリーズなどが代表格ですね。こうしたファンドは基本的にネット証券の投信ポイントでは「制限ファンド」となります。となれば、基本的には制限ファンドとして最も高い還元率を出しているところを利用するべきだと思います。
まず、どこか1社に絞って投資信託への投資を始めるというのであれば、現状だと「SBI証券」を推奨します。
- 低コストのインデックスファンドを考えた時の還元率が一番高い
- 三井住友カードがあれば積立額の0.5%~2%のポイント付与がある
という点です。この二つの合わせ技が使えるという点がSBI証券をおすすめする理由です。クレカによる投信ポイントについては以下の記事もご参照ください。
参考:SBI証券×三井住友カードでクレカで投信積立サービス。0.5%~2%のポイント還元がオトク
同じように「楽天証券」もポイント還元率が高く、楽天カードで積立をすると1%のポイント還元があるためお得ではあります。ただし、2022年4月に保有残高に応じた毎月のポイント付与が終了することになります。
これを踏まえるとこれから投信積立をするならSBI証券の方が強いかなぁというのが個人的な印象です。とはいえ、積立で1%貰えるのはすごく強いので、それぞれで併用していくというのは悪くないです。
参考:楽天カードで投信積立+売却で年間6000ポイントがほぼノーリスクで手に入れる方法
とはいえ、両社とも投信ポイントをめぐる動きは改善と改悪を繰り返しています。SBI証券も一時期は大きく改悪に舵をきったタイミングもあります。今は楽天証券が改悪方向に向かっているターンです。
こういうポイント制度は運用会社の胸三寸で変更されるもので、2年後、3年後も絶対的なものではありません。振り回されてあくせくするより両方使えばいいんじゃないの?というのが私のスタンスです。
ちなみに、私はSBI証券も楽天証券も両方で毎月クレジットカードで5万円ずつ積立しています。これだけで年間12000円分のポイントをもらってます。
以上、投資信託の保有ポイント制度でネット証券を比較してみました。
今、一番おすすめのモバイル回線は「楽天モバイル」です。
今は『楽天モバイル』が最強。楽天リンクを使えば通話かけ放題だし、パケットも使い放題で月々3,168円。データ通信をあんまり使わない人は1,078円で回線を維持できます。
さらに、家族と一緒なら110円OFF。
今なら三木谷社長からの特別リンクから回線を作ると、他社からMNPで14,000ポイント。新規契約なら11,000ポイントもらえるぶっ壊れキャンペーン中。