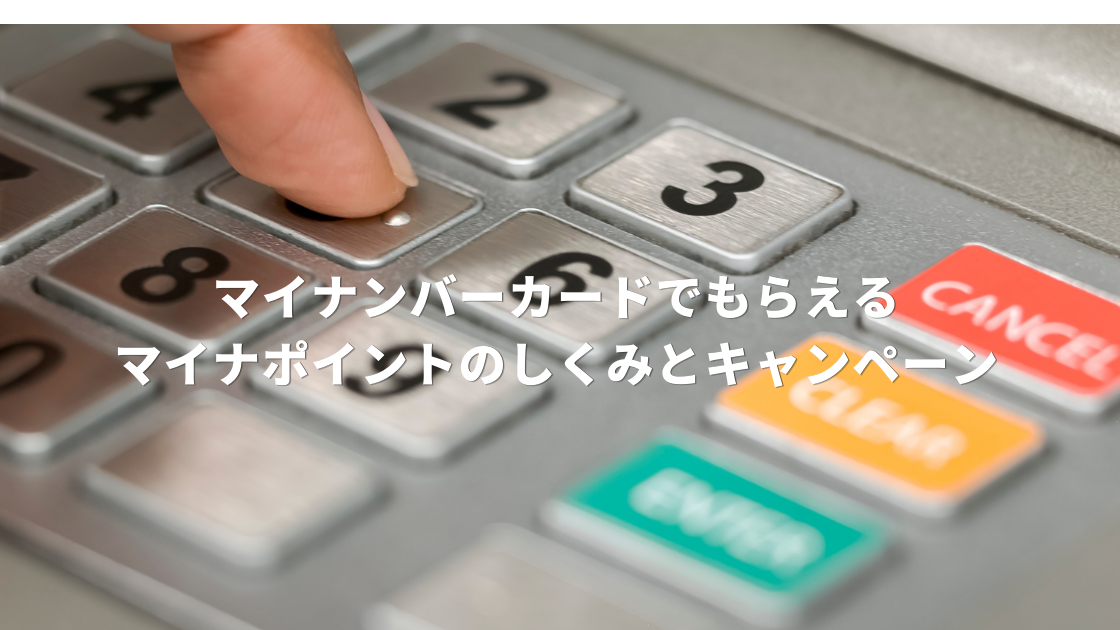児童手当の現況届の「監護」「生計関係」の意味や所得制限・所得上限の計算方法

児童手当とは中学生修了までの児童がいるご家庭を対象に支給される手当金制度です。その児童手当について受給要件を確認するための書類が“児童手当現況届”というものです。
多くの自治体は6月上旬にこの現況届を郵送しており、6月末までに提出を求めています。これは児童手当を受けるためには必ず行う必要があるものです。今回はそんな児童手当現況届の書き方や受給可能な金額、所得制限の計算方法についてまとめていきます。
2021年度の現況届は印鑑が不要に。2022年度からは現況届は原則として提出不要になりました。
そもそも児童手当とは?
児童手当とは、中学生以下の子どもがいる家庭に給付される公的な手当です。
児童手当という名称は過去も使われており、2019年(令和元年)現在の児童手当は「新児童手当」と呼ばれることもあります。子どもをめぐる公的な手当(支援)については下記のような変遷があります。
| 支給年齢 | 支給金額 | 所得制限 | |
|---|---|---|---|
| 旧児童手当 ~2010年3月まで |
小学校卒業 | 3歳未満:1万円 3歳以上:原則5,000円(第3子以降は1万円) |
あり。一定額をこえると支給額はゼロになる。 |
| こども手当 ~2011年9月まで |
中学校卒業 | 一律:1.3万円 | なし |
| こども手当 ~2012年5月まで |
中学校卒業 | 3歳未満:1.5万円 小学校卒業まで:1万円(第3子以降は1.5万円) 中学校卒業まで:1万円 |
なし |
| 新児童手当 2012年6月~ |
中学校卒業 | 3歳未満:1.5万円 小学校卒業まで:1万円(第3子以降は1.5万円) 中学校卒業まで:1万円 |
あり。一定額(会社員の夫と専業主婦の妻、子供が2人いるモデル世帯で夫の年収が960万円以上)を超えると支給額は月額5,000円になる(当面の間) |
| 2022年10月~ | 中学校卒業 | 変わらず | 所得制限の特例給付に対して所得制限が設けられます。 |
現在の新児童手当の支給額を再度まとめると以下のようになります。
- 3歳未満:月額1.5万円
- 小学校卒業まで:月額1万円(第3子以降は1.5万円)
- 中学校卒業まで:月額1万円(第3子以降も1万円)
おおよそ、制度が変更とならなかった場合には子どもひとりあたり約198万円~208万円が給付(出生~中学校卒業まで)されるということになります。生まれた月によって金額が前後し、一番お得なのは4月生まれ、一番損なのは3月生まれとなります。
なお、児童手当の記載は「月額」ですが、実際の支給は年3回に分けて行われます。4か月分がまとめて入金されるので結構な金額になります。
- 2月(前年10月~1月分)
- 6月(2月~5月分)
- 10月(6月~9月分)
児童手当の現況届は2022年度(令和4年度)より原則提出不要に
児童手当の現況届は毎年6月の提出が必要でしたが2022年より原則として不要になります。一方で現況届が必要な人には6月に現況届が届きます。届いた場合は提出が必要です。
なお、以下の変更があった場合には届け出が必要となります。
- 就職や退職などにより加入する年金が変更になった方(厚生年金→国民年金など)
- 配偶者と婚姻・離婚をした場合
- 市外に住む配偶者が転居した方
児童手当の現況届でチェックされる項目
児童手当の現況届で確認されるのは以下の点です。
- だれが児童手当の支給対象であるのか?
- 所得制限を超えていないかどうかの確認
だれが児童手当の支給対象であるのか?
児童手当は子どもが対象の手当ですが、お金はその子どもを監護・保護している人です。夫婦と子どもが同居している場合、最も収入が多い人が対象者となります。これはわかりやすいですね。
一方で別居している場合は同居している人が請求する必要があります。父と母が別居中であり、収入は父の方が大きいけど、子は母と同居している場合、母が請求者となります。
ただし、夫が単身赴任などにより別居しているものの生計は同一であるという場合は、夫が夫の住む市区町村に対して請求することになります。
監護の有無とは?
監護の有無というのは要するに面倒を見ているってことです。児童手当は子どもの監護・保護をしている方に支給されるものです。なので、特別な事情がない限りは、監護の有無は「有」になるはずです。
生計関係の同一、維持とは?
これは少し表現がややこしいのですが、ほとんどの方は「同一」になるはずです。
| 同一 | 児童が、受給者自身の子どもである、未成年者後見人がいる、または父母指定者がいる場合で、受給者がその児童と生計を同一にしているケース。通常はこちらになります。 |
|---|---|
| 維持 | 児童は受給者自身の子どもではないが、受給者がその児童の生活費の大半を出しているケース。同居していてもいいし、別居でも構わない。 |
同居別居の差と説明している方もいますが、正しくありません。上記の説明通り、大半の方は「同一」となるはずですが、状況が複雑な方はお住いの市役所に直接確認をしたほうがよろしいかと思います。
所得制限を超えていないかどうかの確認
こども手当から(新)児童手当へ移行した中で大きな変更点は「所得制限」が付いたということです。また、2022年からは「所得上限」も設定されています。
| 扶養親族 | 所得制限 | 所得上限 | ||
|---|---|---|---|---|
| 所得制限額 | 収入の目安 | 所得制限額 | 収入の目安 | |
| 0人 | 622万円 | 833.3万円 | 858万円 | 1071万円 |
| 1人 | 660万円 | 875.6万円 | 896万円 | 1124万円 |
| 2人 | 698万円 | 917.8万円 | 934万円 | 1162万円 |
| 3人 | 736万円 | 960万円 | 972万円 | 1200万円 |
| 4人 | 774万円 | 1002万円 | 1010万円 | 1238万円 |
| 5人 | 812万円 | 1040万円 | 1048万円 | 1276万円 |
①所得制限
2022年現在、所得制限を超えた場合、給付額が通常よりも減らされ、一律5,000円(月額)の特例給付となります。仮に1万円と比較すれば年間で6万円(一人あたり)も減ってしまう計算となります。
所得制限額は以下の通りとなっており、扶養親族の数によって変わってきます。世帯の合算所得ではなく、受給資格者と配偶者それぞれ単独の所得で判定し、所得の高い方が受給資格者となります。夫婦で合算する必要はありません。
②所得上限
2022年より所得上限額も設定されており、これを超えた場合特例給付も行われなくなります。所得上限を超えた方で翌年以降に所得上限を下回った場合には認定が必要になります。
所得制限額を計算しよう
サラリーマンの方の場合は「源泉徴収票」をご用意ください。
<計算式>
審査対象所得=所得額 – 控除額 – 8万円
では、源泉徴収票にある「給与所得控除後の金額」を見てください。ここから以下の金額を引きます。
ちなみに、該当なしという方も多いと思います。その金額から8万円(社会保険料控除+生命保険料控除相当)を差し引く形になります。
仮に給与収入が900万円の場合、給与所得控除は「900万円×10%+1,200,000円=210万円」となります。給与所得控除は690万円になりますね。そこから8万円を引くので審査対象所得は682万円ということになります。
児童手当における扶養親族等とは何か?
所得額が計算されたら、次は縦軸となる「扶養親族等」がいったい何人なのかが重要になります。これは以下のような人が該当します。
- パート収入が年103万円以下の配偶者(扶養範囲内)
- 扶養している子ども
- 扶養しているその他親族
※前年の12月31日時点が計算の対象となります。
たとえば、妻はパートで103万円以内で働いており、小学生と幼稚園の児童2名を養育している場合の扶養親族等は3名になります。
3名の場合の所得制限額は736万円です。先ほど計算された審査対象所得は682万円なので、所得制限以下ということで、満額の児童手当が支給されるということになります。
所得制限の対象になりそうならiDeCoや両親の扶養が有効
もし、自分の年収が今年(来年)の所得制限に引っかかりそうなのであれば、iDeCo(個人型確定拠出年金)が有効です。将来の年金の積立を非課税で有利に行うことができる上、審査対象所得の計算においてiDeCoの拠出金は差し引けます。
[bloglink url=”https://money-lifehack.com/asset-management/1348″]
恣意的な運用はできませんが、高齢の両親などがいる場合は、自分の扶養に入れることも一つの手です。扶養というと同居のイメージがあるかもしれませんが、生計を一にするというのは必ずしも同居を要件としません。仕送り等で実質的に扶養しており、一定の要件を満たせば自己の扶養親族とすることができます。
[bloglink url=”https://money-lifehack.com/tax/4924″]
児童手当の現況届以外の手続きが必要なケース
以下に該当する場合は、市役所などに連絡をして現況届を提出する以外の手続きが必要になります。
- 離婚や別居により養育する者が変わった
- 請求者がその市区町村から転出している(単身赴任を含む)
- 請求者が公務員になった
- 印字されていない児童を養育している
- 印字されている児童を養育していない
児童手当の現況届を出し忘れたらどうしたらいい?
児童手当の現況届には提出の期限があります。
この現況届を忘れていると、6月分以降の児童手当の支給がストップしてしまいます。実際は6月~9月が10月支給されますが、この10月分がもらえなくなります。
提出が少し過ぎたからといって手当が減額されることはありませんが、支給日が遅くなる場合があります。もし、出し忘れたとしても、気が付いたらすぐに発送するようにしましょう。
なお、支給が停止されて気が付いたという場合も、現況届を提出すれば再開されますし、支給されなかった分もさかのぼって受給可能です。短期間なら現況届の郵送でも構わないと思いますが、数か月単位で送れた場合は、市役所に手続き方法を確認しましょう。
ちなみに、そこまでする方はいないと思いますが、児童手当の時効は2年間なので、2年放置すると受給資格が消滅するのでご注意ください。
現況届を紛失した(あるいは届いていない)場合はどうすればいい?
児童手当の現況届は市役所に連絡をすれば再発行が可能です。
6月中旬になっても届いていない、あるいは受け取ったけど紛失をしてしまった……という場合は早めに市役所に連絡をして再発行してもらいましょう。
なお、届いていない可能性として、別の市区町村に引っ越しをしており、新しい住所での「児童手当認定請求書」を提出していない可能性もあります。
このケースでは、別途手続きが必要になりますので、市区町村の窓口に「健康保険証」「キャッシュカード(振込先)」「両親の住民税課税証明書(1月1日時点で居住の役所で発行)」「両親のマイナンバー」「印鑑」をもっていき手続きしましょう。
以上、児童手当の現況届の言葉の意味や所得制限の計算方法、忘れたときの対応などについてまとめました。
今、一番おすすめのモバイル回線は「楽天モバイル」です。
今は『楽天モバイル』が最強。楽天リンクを使えば通話かけ放題だし、パケットも使い放題で月々3,168円。データ通信をあんまり使わない人は1,078円で回線を維持できます。
さらに、家族と一緒なら110円OFF。
今なら三木谷社長からの特別リンクから回線を作ると、他社からMNPで14,000ポイント。新規契約なら11,000ポイントもらえるぶっ壊れキャンペーン中。