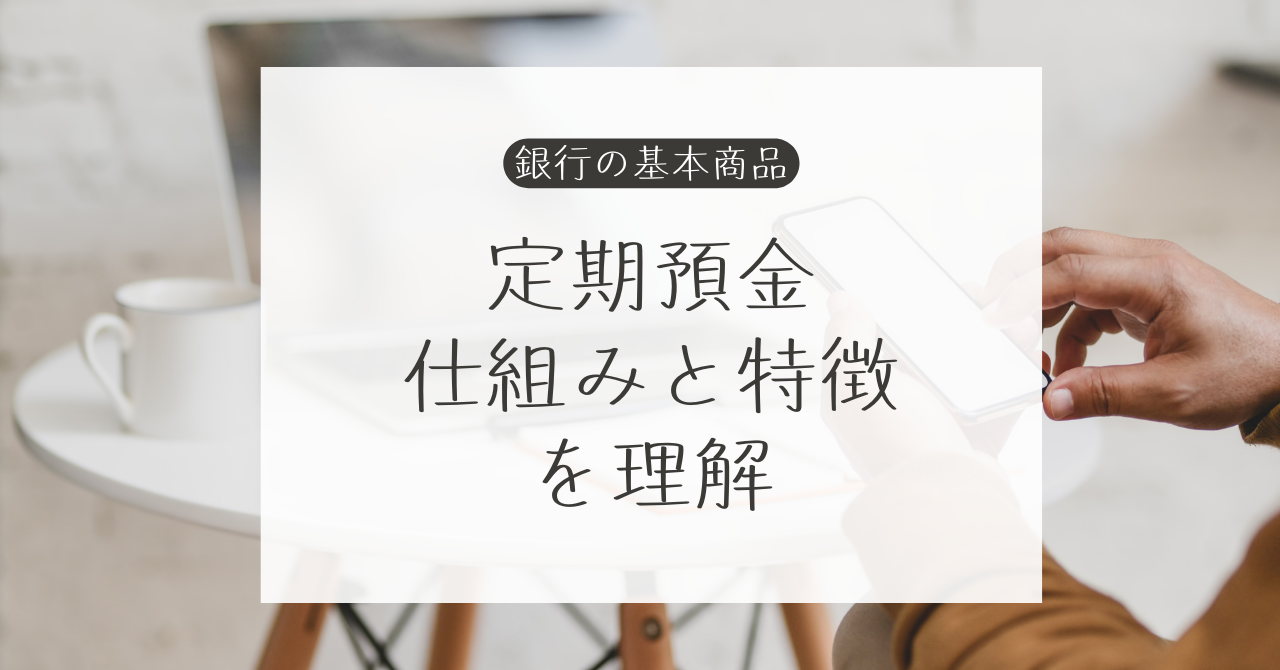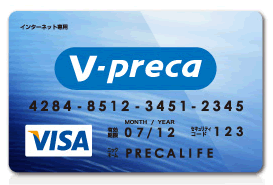2013年3月29日、孫への教育資金贈与を非課税とする税制改正案が可決、成立しました。これに伴い、祖父母が孫1人あたり1500万円まで教育資金として金融機関に預ける場合、贈与税が非課税となるという制度です。
2013年3月29日、孫への教育資金贈与を非課税とする税制改正案が可決、成立しました。これに伴い、祖父母が孫1人あたり1500万円まで教育資金として金融機関に預ける場合、贈与税が非課税となるという制度です。
当初は2015年までの期間限定の措置でしたが、延長が重ねられており、現在のところ2021年3月末までの実施が確定してます(それ以降も延長される可能性があります)。
今回はそんな教育資金の非課税贈与の仕組みと、それを可能とする信託銀行のサービスである「教育資金贈与信託」という商品について、その内容や特徴、利用にあたっての注意点などを紹介していきます。
教育資金の一括贈与非課税措置
まず、この信託サービスについては2013年4月からスタートした「教育資金の一括贈与非課税措置(直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の非課税)」という税制改正に伴うものとなっています。
これは、父母や祖父母、曾祖父母など直系の尊属による一括贈与を非課税とするものです。
非課税枠は受贈者(贈与を受ける人)1名あたり1500万円までとなっており、この金額の範囲内であれば、以下の目的で利用される場合、贈与税はかかりません。
入学金、授業料、入試検定料、通学にかかる定期券代、給食費、修学旅行費、学校を通じて購入する教材、学用品代等
<下記に該当するものは500万円までなら非課税>
- 学習塾や予備校、家庭教師の授業料
- 水泳やピアノ、習字などの習い事に関する月謝
当初は2015年までの適用期限でしたが、2度延長されており、現在は2021年3月31日までが適用期限となります。
教育資金贈与信託のしくみ
三井住友信託銀行や三菱UFJ信託銀行、りそな銀行は2013年4月1日からこの教育資金贈与信託を開始しました。いずれも契約手数料などは無料。
教育資金贈与信託は下記のような流れで行います。
- 祖父母が孫1名あたり1500万円を上限に教育資金贈与信託にお金を預ける
- 孫は、専用の通帳等を受け取り学校・塾・習い事などの教育費であればいつでも回数制限なしにそのお金を引き出すことができる(その際は証明できる領収証等が必要
なお、孫が非課税で引き出すことができるのは30歳まででそれ以降でお金を使い残している場合には贈与税がかかった上で払い戻されます。
※教育資金贈与信託のサービスを提供している銀行です。
教育資金贈与信託取り扱い金融機関一覧
- 三井住友信託銀行(孫への想い)
- 三菱UFJ信託銀行
- りそな銀行(きょういく信託)
- みずほ信託銀行(教育資金贈与信託)
- 横浜銀行(教育資金贈与信託)
- 大垣共立銀行(教育資金贈与信託)
商品としては証券会社でも扱えるみたいですが現在は商品提供はないみたいです。
ちなみに、教育資金贈与信託を使わなくても祖父母が孫の教育費等について一括して支払うのではなく、都度支払う(贈与する)のであれば、現行でも贈与税はかかりません。
教育資金贈与信託をつかうことで、将来の分までをまとめて贈与しても非課税となるわけです。
教育資金贈与信託のメリット、デメリット
メリットについては「まとめた贈与ができる」ということ。
暦年贈与といって年130万円までの贈与は基本非課税にできます。ただし、まとまった財産がある方などはチマチマした対策では対応できないかもしれません。
教育資金贈与信託(直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の非課税)を利用すれば最大1500万円を一度に贈与することができる仕組みですので、孫が6人いる方なら一度9000万円分の相続財産を贈与することができます。
ただし、教育資金贈与信託の利用(直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の非課税の利用)については下記の様なデメリットもあることをしっかりと理解しておきましょう。
受け取る側のメリット、デメリット
メリットとしては、こうした税制上の優遇によって祖父母などからまとまった資金を受け取ることができ、自身の教育資金として受け取ることができる点にあります。
一方のデメリットとしては、以下のような制約がかかってしまう点でしょう。
- 30歳までに使い切る必要がある
- 教育資金に用途が限定される
- いちいち信託銀行に領収証を渡す必要があるなど手間がかかる
上記のような問題があります。教育資金贈与信託を使うことで、信託する時点では贈与税はかかりません。しかし、最終的には「教育資金として30歳までに使われる」場合のみが非課税となります。
教育資金贈与信託で使える教育費の例
さらに教育資金として使えるものは多少限定されています。
たとえば、大学生の学費と言う場合、仕送りや住居費、食費などは教育費としては認められません。認められるのは入学金や授業料などです。
「子供の教育に必要な「学費」の目安」によると大学生にかかる費用は私立大学理系(4年)、自宅外通学のケースで1279万円となっていますが、その中で教育資金贈与信託で利用できるのは約520万円程度の授業料と入学金だけとなります。
なお、こうした学校教育以外にも、「学習塾・予備校」「英会話教室」「スイミングなどの習い事」なども教育費として利用可能です。ただし、学校以外の場合は最大で500万円までしか非課税枠として認められないので注意してください。
贈る側が考えておきたいデメリット
- 単純にその年の教育費を渡すならそもそも非課税
- 相続税対策のやりすぎで老後破産に陥るリスクも
- 誰にあげるかでトラブルになることも
そもそも、親が祖父母などが生活費などを「必要な時」に渡す場合は非課税です。ですから教育資金などを「その都度」渡す前提であれば、教育資金贈与信託などを遣う必要はありません。年に100万円渡そうが200万円渡そうが非課税です。
また、教育資金の一括贈与は相続税対策になるものの、それだけを考えて、自分自身の老後生活の足かせになるリスクがあります。「老後破綻への道?子どもや孫への生前贈与の注意点」でも書いていますが、子どもや孫のためにと生前贈与をすることで、将来の自分自身が生きていくための財産を失ってしまうようなケースもあります。
最後に、子どもが複数人いて、孫の数が違う場合などもトラブルのもとです。たとえば孫がいる相続人といない相続人との間で不公平感が生まれるケースもあるでしょう。よかれと思った贈与が返って争続(そうぞく)を生む結果になってしまうかもしれません。
相続税対策なら別の方法もある
ちなみに、「結婚・子育て資金の一括贈与」という類似の制度もスタートしています。
[bloglink url=”https://money-lifehack.com/tax/3205″]
また、このような目的を絞った方法ではなく、最初の方にも書きましたが「暦年贈与」を用いた相続税対策も有効です。暦年贈与に関しても信託銀行は「暦年贈与信託」などの信託サービスを行っています。
こうしたサービスの利用も考えながら、適切な贈与の仕方を考えていきましょう。
お金を確実に非課税で贈与する「暦年贈与信託」とは何か?もぜひご一読ください。
今、一番おすすめのモバイル回線は「楽天モバイル」です。
今は『楽天モバイル』が最強。楽天リンクを使えば通話かけ放題だし、パケットも使い放題で月々3,168円。データ通信をあんまり使わない人は1,078円で回線を維持できます。
さらに、家族と一緒なら110円OFF。
今なら三木谷社長からの特別リンクから回線を作ると、他社からMNPで14,000ポイント。新規契約なら11,000ポイントもらえるぶっ壊れキャンペーン中。