会社を退職した後の健康保険。任意継続と国民健康保険はどちらがお得?
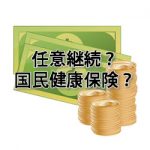 会社を退職して自営業、フリーランスなどとして生きていく、あるいはしばらく休業したい。こうした時に考えなければならないものの一つに健康保険があります。
会社を退職して自営業、フリーランスなどとして生きていく、あるいはしばらく休業したい。こうした時に考えなければならないものの一つに健康保険があります。
病気や怪我をした時の治療費に対する公的な保険で、必ず加入する必要があります。会社を辞めた場合には、その会社の健康保険の「任意継続を使用する」か、「国民健康保険に加入し直す」のどちらかを選択する必要があります。
また、配偶者が働いているのであれば「配偶者が加入する社会保険の被扶養者になる」という選択もあります。どの方法が金銭的に、制度的にお得なのでしょうか?それぞれを比較しましょう。
これから収入の見込みがない場合
まず、あなたが退職しその後収入の見通しがなく、配偶者が社会保険に加入しているという場合であれば「被扶養者になる」というのが一番お得です。被扶養者になっても扶養者の保険料は変わりません。
ただし、被扶養者になるには所得制限(見込み年収130万円未満)であることに加え、失業給付(失業保険)を受給していないことなどが条件となります。
参考:働くときの103万円、130万円(106万円)の壁の存在
被扶養者になれない場合は「国民健康保険」か「任意継続」の二つから選択する必要があります。
国民健康保険と任意継続の比較
国民健康保険は、地域の健康保険で市町村が運営しています。一方の任意継続というのは、これまで加入していた「協会けんぽ」や「健康保険組合」にそのまま加入するというものです。
特別に手続きをしない場合、会社を退職したら「国民健康保険」に加入することになりますが、退職後20日以内に健康保険組合窓口で手続きをすることにより「任意継続(任意継続被保険者制度)」が可能です。
どちらがお得なのでしょうか?それはあなたの年収や家族の有無などによって変わってくることになりますので、一概にこうするのがお得とは言えません。ただし、結論を先にいえば、社会保険の任意継続の方が一般的にはお得になるかと思います。
なお、国民健康保険(国保)と健康保険(社保)の違いについては「国保(国民健康保険)と健保(社会保険の健康保険)の違いとどちらがお得かどうかの比較」でも詳しく説明しているのでこちらもご覧ください。
社会保険の任意継続の計算
任意継続は今までの会社の健康保険に最大2年間継続して入ることができるという制度です。退職した前日までに2カ月以上の社会保険加入が前提となります。
在職中は保険料は労使折半(半分会社負担)でしたが、任意継続の場合は全額自己負担となります。保険料は在職時の「標準報酬月額(月収)」から決められます。
具体的な金額は各健康保険(協会けんぽ)によって決められています。
なお、任意継続の場合、標準報酬月額は28万円が上限となっているので、それ以上の収入があっても健康保険料は28万円の時の保険料が上限となります。
ちなみに、東京都(H26.6月~)の協会けんぽ加入のケースでの健康保険料の上限は月額「27,916円(40歳未満)」「32,732円(40歳以上)」となります。月収の目安が28万円未満なら保険料はもっと安くなります。
ちなみに、後ほど説明しますが配偶者や子供などの被扶養者がいる場合であっても保険料は変わりません。この点は後ほど説明する国民健康保険とは大きく異なります。
国民健康保険料の計算
国民健康保険料は世帯の「前年所得」によって決まります。ただし、計算の方法はお住まいの自治体によって異なり、実際に必要な金額も変わってきます。お住まいの市区町村の国民健康保険の窓口に問い合わせをするのが一番確実です。
国民健康保険には扶養の概念はなく、世帯単位での加入となります。そのため、収入に対する保険料「所得割り」だけでなく、扶養する家族が増えるほど「均等割り」という形で保険料が増加します。
一方で健康保険(健保)には扶養の概念があり、年収見込みが130万円未満といった条件を満たせば追加の保険料無しで健康保険に加入できという違いがあります。
また、自治体によっても大きく違ってきます。保険料が高い低いは自治体によっても違います。さらに、「資産割り」というものもあり、マイホーム所有のように固定資産をもっていると健康保険料が高くなる自治体もあります。
このように、国民健康保険の場合、社会保険と異なって保険料の割り増し要因が多いということになります。収入のない家族が多いご家庭やマイホームなどの固定資産税がかかる資産を持っている家庭は不利になる可能性が高いです。
国民健康保険が割高となるケース
- 扶養家族(妻や子供)がいる
- 固定資産税を払っている
- 国民健康保険料が高い自治体に住んでいる
国民健康保険が割安となるケース
- 独身世帯である
- 前年の所得が低かった
任意継続が使えるなら任意継続がお勧め
実際に払うべき保険料は各自治体によって違います。国保の保険料は前年所得で決まりますので、昨年度の源泉徴収票をもとに各自治体のホームページで計算方法を見ればおおよその金額は計算できます。
ただ、月収が25万円以上ということであれば、健康保険(健保)の方が保険料は訳すなるケースが多いかと思います。子供がいるというケースや配偶者を扶養に入れているというケースならなおさらです。
健康保険でもいいというのは、「独身」「前年収入が少ない」といったようなケースに該当する方でしょう。ただ、任意継続を選択していれば、今は独身でも今後2年の間に結婚を予定しているというような場合であれば、結婚後の配偶者を扶養に入れることも可能です。
実は退職日は超重要
なお、配偶者の扶養に入ることができる(寿退社含む)というのであれば、退職日は月末の1日前がお得です。この場合、退職月の社会保険料の負担が必要なくなります。
それ以外の人は月末にしましょう。
月末ならその月まで会社の社会保険に入れますが、月末でないとその月の社会保険料(健康保険料+厚生年金保険料)の支払いは不要になりますが、代わりに国民家健康保険料+国民年金保険料を払う必要があります。
詳しくは「会社を辞めるのは月末?月末の1日前?社会保険料負担で考える退職日」でもまとめています。
以上、会社を退職した後の健康保険。任意継続と国民健康保険はどちらがお得?というお話でした。
今、一番おすすめのモバイル回線は「楽天モバイル」です。
今は『楽天モバイル』が最強。楽天リンクを使えば通話かけ放題だし、パケットも使い放題で月々3,168円。データ通信をあんまり使わない人は1,078円で回線を維持できます。
さらに、家族と一緒なら110円OFF。
今なら三木谷社長からの特別リンクから回線を作ると、他社からMNPで14,000ポイント。新規契約なら11,000ポイントもらえるぶっ壊れキャンペーン中。














