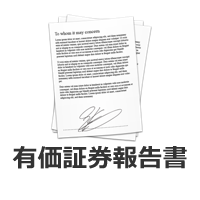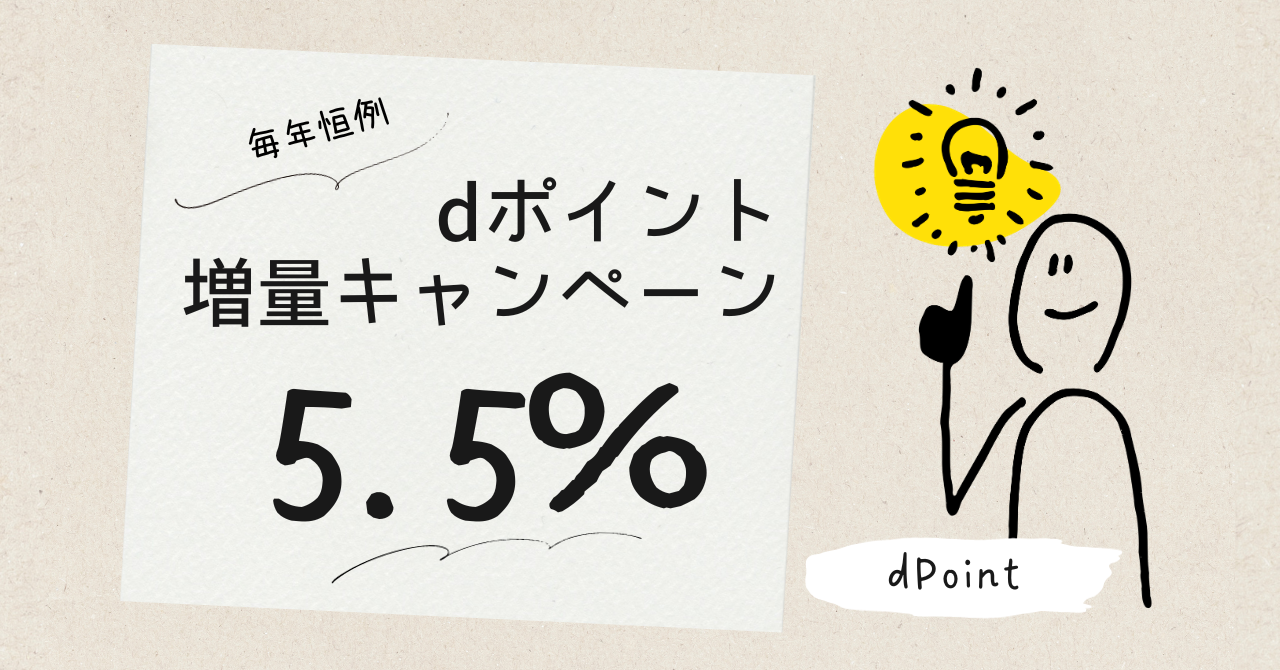自分の自動車をレンタルして収益化するカーシェアリング(マイカーシェア)で副業
 カーシェアリングの利用者が増加しています。最大手としてはタイムズが運営しているタイムズカープラスが代表的ですね。こちらはタイムズ(パーク24)が車を確保した上で、時間貸しをするという旧来のレンタカーに近いサービス内容となっています。
カーシェアリングの利用者が増加しています。最大手としてはタイムズが運営しているタイムズカープラスが代表的ですね。こちらはタイムズ(パーク24)が車を確保した上で、時間貸しをするという旧来のレンタカーに近いサービス内容となっています。
その一方で、今回紹介するのは自動車の個人間による貸し出し(シェアリング)となります。
Airbnb(エアビー)が自宅を宿泊施設としてシェアするように、自分が持っているけど使っていない時間だけ自動車をシェア(貸し出す)というサービスになります。
貸し手(レンダー)となれば、貸出に応じて収益化することも可能になります。今回はそんな自動車のシェアリングサービスを利用しての副業、副収入についてまとめていきます。
カーシェアリングのマッチングサイトの仕組み
個人間でカーシェアリングを利用するときは、マッチングサイトを利用して行います。
マッチングサイトには貸したい人の自動車情報が登録されており、それを借りたい人が申し込みをしてレンタルするという流れになっています。
こうした自分の資産を貸し出すことで収益化するというビジネスモデルは近年様々な分野で広がっていますね。多くの方がご存知の自分の部屋を貸すという民泊シェアリング(Airbnb)の他、先日「使っていない駐車場やガレージを収益化できるakippaの駐車場シェアリングサービス」でも記事にした駐車場・空き地のシェアリング。そして今回紹介する自動車のシェアリングがあります。
マイカーシェアで儲けるためのコツや注意点
続いては、カーシェアリングのマッチングサービスを利用する上で貸し手としてのコツや注意点などをまとめていきます。
人気が高い車種を用意すると借り手が増えやすい
こうした個人間の自動車のカーシェアリングは、高級車や特殊な車が人気です。
なぜなら、普通に実用的な意味で車を借りたいというのであれば、タイムズカープラスのような専門のカーシェアリングサービス、レンタカーサービスを利用するほうが使い勝手がいいです。
それでもこうしたサービスを使って車を借りたいというのは、そういったカーシェアリングサービスやレンタカーでは借りることができない(乗ることができない)車を使ってみたいからに違いないです。ポルシェやベンツといった高級外車のほか、スポーツカーやオープンカーのように一度は乗ってみたいけど、買うにはちょっと……といった車もいいですね。
他に人気がたさそうなものとしては、輸送のための大型バンや軽トラなども意外と需要がありそうです。
個人間トラブルは自分たちで解決する必要がある
自動車という外を走るものだからこそですが、傷をつけた、つけていないなどでトラブルになるケースも考えておく必要があります。
こうしたカーシェアリングのマッチングサイトはあくまでもマーケットに過ぎず、こうしたトラブルは個人間で解決するというのが基本になります。こうしたトラブルにならないように傷や凹みなどに対する事前確認や万が一の場合の対応についてはあらかじめ取り決めをしておくことをお勧めします。
傷や事故についての補償は要注意
それでも事故というものは絶対に発生しないとは言えません。
カーシェアリングで貸している車が事故にあうというリスクはもちろんあります。自動車の事故において自動車損害賠償保障法では、交通事故の責任は「運行供用者」も責任を負う事になっています。
運転供用者は「自己のために自動車の運行の用に供する者」であり、簡単にいえば車両の保有者も含まれることになります。つまり、貸した車が人身事故を起こした場合、最悪の場合、貸し手自身が賠償責任を負う事になるのです。
それぞれのカーシェアリングのマッチングサイトでは借り手が事故を起こしたときの保険加入を求めているので、万が一の場合の事故で問題になることは少ないでしょう。
ただ、こうした保険では車両の損害や盗難などが補償されないケースがあります。
そうした場合は自身の保険(車両保険等)を利用する必要がありますが、翌年以降の保険料負担がアップすることになります。
参考:自動車保険の事故あり係数と適用期間、自動車保険・車両保険節約の賢い考え方
また、カーシェアとして貸し出す場合は、使用目的を業務としておく必要がありそうです。していない場合は保険が効かない可能性があります。
マイカーシェアのマッチングサイト比較
2018年2月28日現在でのカーシェアリングサービスを比較していきます。記事公開当初と変わっている部分は修正しております。
エニカ(Anyca)
 株式会社DeNAが運営。
株式会社DeNAが運営。
登録台数は順調に増加しており、全国的なサービス展開を行っています。東京都内だと1154台が登録されています(2018年2月28日現在)。
登録は無料でプラットフォーム手数料は10%になっています。エニカ(Anyca)におけるマイカーシェアの料金授受は、レンタルによる貸し借りではなく、個人所有車両の「共同使用契約」という形をとっています。これは道路運送法における例外規定を利用したものです。
そのため、実際の利用は1日でも契約期間は6か月となっているのです。また、個人間取引が前提となるため、法人は利用できません。
事故が起きたときの保険はどうなっている?
保険のシステムは明快で、ドライバーが東京日動火災の1日自動車保険(車両補償付)に加入する仕組みとなっています。オーナーとしてはカフォレのような保険に入らなくてよいのはいいですね。
dカーシェア
 NTTドコモが運営。2017年末にサービスを開始した、レンタカー、カーシェアリング、マイカーシェアの横断検索サイトです。マイカーシェアとして登録を受け付けています。Anyca(エニカ)と同様にマイカーシェアは共同使用契約という形をとっています。
NTTドコモが運営。2017年末にサービスを開始した、レンタカー、カーシェアリング、マイカーシェアの横断検索サイトです。マイカーシェアとして登録を受け付けています。Anyca(エニカ)と同様にマイカーシェアは共同使用契約という形をとっています。
dカーシェアを通じて車をシェアするこちにより維持費の節約や収益化が可能になります。
マイカーシェアに関しては、個人間トラブルに発展する可能性(リスク)もあるため、ある程度大きな会社の方がサポート面も含めて安心できます。
[bloglink url=”https://money-lifehack.com/savings/share/15633″]
事故が起きたときの保険はどうなっている?
ドライバーは東京海上日動が提供する1日自動車保険に加入するのが必須となっています。
カフォレ(CaFoRe)
 株式会社WAKEが運営。
株式会社WAKEが運営。
登録台数は全国で1532台となっており、エニカに抜かれてしまいました。
登録は無料で、実際に貸し借りが成立して取引が完了した段階で10%がかかります(落札代金から差し引かれた代金が振り込まれます)。
ちなみに、CaFoReの場合、有償で車を貸し借りするのではなく、車自身は無料で貸すけれども、その出品者との独占的交渉権を行うという対価としての価格が設定されています。
分かりにくいのですが、これはカーシェアが道路運送法の違反にあたる可能性があるための回避策としてこのような形になっています。
事故が起きたときの保険はどうなっている?
実際に自動車を貸し出す際にはレンダー補償に加入する必要があります。月額1,080円~3,240円の保険料となります。補償内容を見る限りこれはかなり微妙な感じです。
1日単位の貸し借りなのになんで月額の保険に加入しなければいけないのでしょうか。月額だと1日だけしかレンタルされなくても1カ月の保険料を払うので無駄になりそうです……。
ちなみに、保険は借り手(ドライバー)も同様に保険に入りますが、こちらも月額制となっています。
マイカーシェアは副業として儲かる?
まだ、サービスとしては試行錯誤に近い段階でもあることから、利用者も特段多いわけではありません。
Airbnbの民泊ビジネスが旅館業法などとの兼ね合いでグレーゾーン的な部分があるのと同様に、カーシェアリングの個人間取引・マッチングサイトについても道路運送法という法律との兼ね合いでややグレーな部分があります。
これはAnycaやdカーシェアなどのサービスがカーシェアリングの対価を「貸し出しによる料金」としていないことからもわかります。今は規模も小さいのでお目こぼしされているだけかもしれませんね。
その一方で、エアビーの民泊で儲けている人が多数いるように、カーシェアリングの個人間取引も規模が拡大して貸し手の数が増え利便性も上がれば大きな市場になる可能性もあります。
現段階では都心が中心のようですので、都心で自動車をお持ちの方で興味がある方は少し検討してみてもいいかもしれませんね。
今、一番おすすめのモバイル回線は「楽天モバイル」です。
今は『楽天モバイル』が最強。楽天リンクを使えば通話かけ放題だし、パケットも使い放題で月々3,168円。データ通信をあんまり使わない人は1,078円で回線を維持できます。
さらに、家族と一緒なら110円OFF。
今なら三木谷社長からの特別リンクから回線を作ると、他社からMNPで14,000ポイント。新規契約なら11,000ポイントもらえるぶっ壊れキャンペーン中。