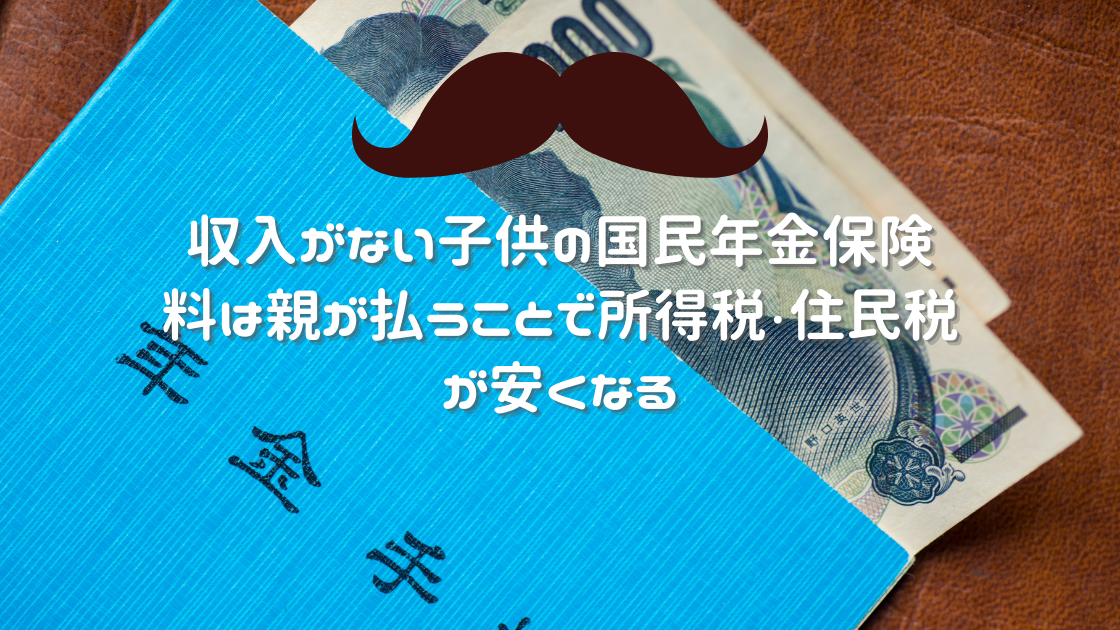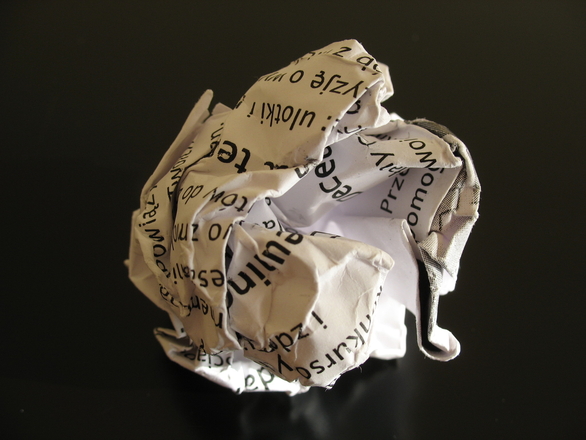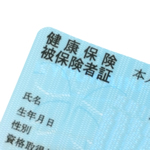産休・育休の間は共働きでも配偶者控除。妻は夫の扶養に入りましょう
 共働きをしていたけど、子どもの出産や育児のために産休・育休を取られるママさんも多くいらっしゃるでしょう。
共働きをしていたけど、子どもの出産や育児のために産休・育休を取られるママさんも多くいらっしゃるでしょう。
この時、復職するまでの一年間ないしは二年間になりますが、妻は夫の扶養(税法上)に入ることができます。出産手当金や育児休業給付金をもらっている方でも大丈夫!これらは“非課税”扱いになっているからです。
手続きも年末調整の時に夫が申告するだけでOKです。2018年以降は配偶者控除(特別控除)が拡大されたことで、年の途中で育休・産休に入った方でも対象になる方が増加するはずです。忘れないように手続きしましょう。
産前産後の出産手当金や育休中の育児休業給付金は非課税
働きながら妊娠して出産、そして復職する予定の場合、健康保険や雇用保険から産休・育休中は資金的な給付があります。
| 給付元・受給資格 | 内容 | |
|---|---|---|
| 出産手当金 (産前産後休暇) |
健康保険 | 社会保険に加入している女性が受け取ることができる手当金です。 産前休暇、産後休暇のお休みの間のお給料を手当てしてくれる手当金となります。健康保険の“標準報酬月額の2/3”を受け取ることができます。 |
| 出産育児一時金 | 健康保険・国民健康保険 | 健康保険に加入している人すべてが受け取ることができる一時金です。健康保険または国民健康保険に加入している人が受け取ることができます。1児あたり42万円(一律)です。 |
| 育児休業給付金 | 雇用保険 | 産後(8週間・56日)を経過したのちで、1歳にみたないこどもを養育する男女労働者(雇用保険加入者)が受け取れる給付金です。条件は雇用保険加入なので、パートやアルバイトの方でも週20時間以上働いているなら利用できる制度です。 |
[bloglink url=”https://money-lifehack.com/working/3667″]
これらの給付の内、出産手当金、育児休業給付金は休業中の給料補償的な面があります。ただ、これらの収入は、税法上は所得(収入)として扱われないことになっています。
産休や育休に入るタイミングにもよりますが、その時期によっては1年の税法上の収入がゼロに近いということもありえます。
産休中、育休中は税法上の扶養に入れる可能性が高い
税法上の扶養というのは、年間の所得が38万円以下の場合を指します。
サラリーマンやパートの場合は給与所得控除という控除があるので、支給額が年103万円以下という金額なります。ただし、この金額を超えた場合でも、年間の収入が201万円以下であれば、配偶者特別控除を利用することができます。
2018年1月~制度が少し変わり、配偶者特別控除の範囲が拡充されています。
[bloglink url=”https://money-lifehack.com/diary/7275″]
妊娠や出産で会社を休業するのであれば、その年の1月1日~12月31日までに受け取った給料の総額を計算してみましょう。合計額が201万円以下であれば、夫が配偶者控除(特別控除)を利用できる可能性があります。
この時の収入には前述のように出産手当金、育児休業給付金は含みません。
201万円以下なら夫が年末調整で妻を扶養に入れることができる
産休、育休に妻が入る場合、夫がサラリーマンであれば年末調整で配偶者控除(配偶者特別控除)の手続きできます(自営業、フリーランスなら確定申告)。
源泉控除対象配偶者というところに所得の見積もりなどを記入する形になります。
[bloglink url=”https://money-lifehack.com/working/13622″]
書類としてはこれだけになります。
配偶者控除(配偶者特別控除)でどれだけ節税になる?
配偶者控除(配偶者特別控除)でどれだけ節税になるのかは夫の年収(所得税率)や配偶者特別控除の金額によって違います。
仮に夫の年収が600万円で妻の年収が150万円以下の場合、配偶者控除は38万円になります。
節税になるのは所得税率(この場合20%)と住民税率(10%)の合計になりますので38万円×0.3=114,000円になります。
結構な金額ですよね!妻の復職のタイミングとその後の収入にもよりますが、1年間または2年間この控除を受けることができるはずです。
会社によっては夫(配偶者)が扶養手当を受けられることも
扶養手当というのは公的な制度ではなく、あくまでも会社が独自に設けている従業員への手当です。なので、ルールは会社が決めています。税法上の扶養なのか、それとも社会保険上の扶養なのか?あるいはまったく別基準なのか?
これについては夫(配偶者)の会社のルール次第なので確認してもらいましょう。
ちなみに、育休は男性でも取得可能
ご存知の方も多いと思いますが、育児休業は男性でも取得可能で、育児休業給付金についても給付されます。
なので、産休は妻が取るけど、その後は妻は仕事に復帰し、夫が育休を取得、結果として夫が妻の税法上の扶養に入るという方法も取ることができます。
申告を忘れていたとしても5年間はさかのぼることができる!
えー、そうだったの……知らなかったから扶養に入れてなかった……なんて方もご安心ください。
もし、過去に配偶者控除(配偶者特別控除)を申告せずに控除を受けられなかった場合でも5年間はさかのぼって確定申告のやり直しや更生の手続きを行うことでやり直しができます。
- 夫の源泉徴収票
- 妻の源泉徴収票
- 印鑑
- 通帳
をもって、管轄している税務署に行って相談しましょう。それだけの手続きなら税理士にお願いするまでもなく、税務署で相談しながら対応できるはずです。
そんな昔の源泉徴収票なんてない……。という場合は勤務先を通じて再発行をしてもらいましょう。
[bloglink url=”https://money-lifehack.com/tax/3778″]
ちなみに、社会保険については扶養には入れない
今回の記事で紹介している扶養というのは税法上の扶養の話です。
配偶者の扶養という考えはもう一つ“社会保険上の扶養”という概念があります。ただ、産休や育休における話では、籍としては勤務先に残り続けているという状況になります。
そのため、社会保険としては第2号被保険者として残り続けるという形になります。ただ、産休中や育休中は社会保険料の納付が免除されるため、実質的な負担はゼロになります。
もちろん、社会保険料免除期間中も病気やケガなどで健康保険を使うことができますし、年金も納付したことになります。
[bloglink url=”https://money-lifehack.com/working/8775″]
うっかり忘れないように手続きを
- 産休中、育休中の手当は収入(所得)にならない
- 配偶者控除(配偶者特別控除)の拡大で年の途中での育休でも可能性アリ
- 節税効果は1年に10万円以上になることも
手続き自体は夫が、その年の年末調整で扶養対象配偶者とし申請するだけで手続きはすみます。これまでずっと共働きだったからということで、そのままにして、あとからシマッタ……とならないようご注意くださいね。
以上、産休・育休の間の妻は夫の税法上の扶養に入ることができ、配偶者控除(配偶者特別控除)が受けられるというお話でした。
今、一番おすすめのモバイル回線は「楽天モバイル」です。
今は『楽天モバイル』が最強。楽天リンクを使えば通話かけ放題だし、パケットも使い放題で月々3,168円。データ通信をあんまり使わない人は1,078円で回線を維持できます。
さらに、家族と一緒なら110円OFF。
今なら三木谷社長からの特別リンクから回線を作ると、他社からMNPで14,000ポイント。新規契約なら11,000ポイントもらえるぶっ壊れキャンペーン中。