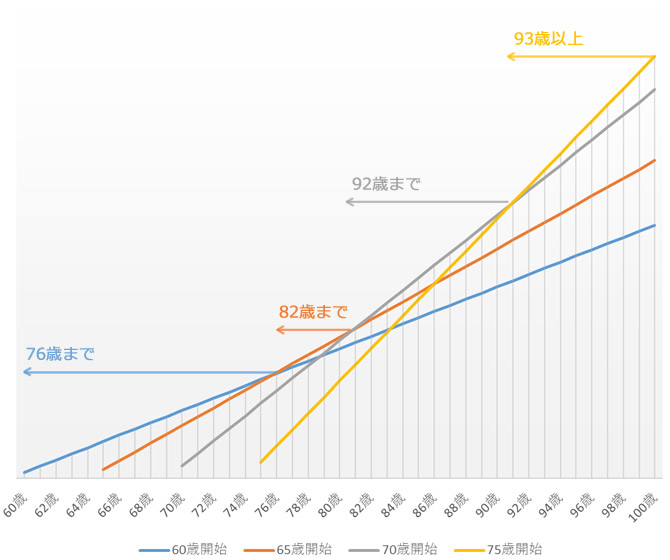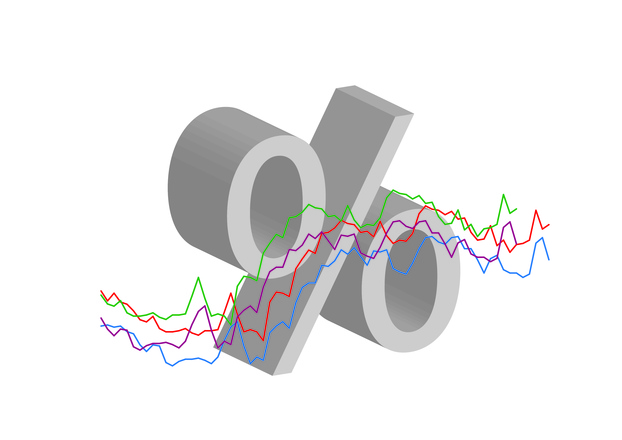公務員が個人型確定拠出年金(iDeCo)に加入するメリット、デメリット
 2017年1月から従来は加入できなかった公務員の個人型確定拠出年金への加入が解禁されます。比較的安泰といわれた公務員の年金制度(共済年金)はサラリーマンが加入している厚生年金よりも掛金や老後の受取金額などが優遇されていました。
2017年1月から従来は加入できなかった公務員の個人型確定拠出年金への加入が解禁されます。比較的安泰といわれた公務員の年金制度(共済年金)はサラリーマンが加入している厚生年金よりも掛金や老後の受取金額などが優遇されていました。
ところが、2015年10月に実施された「共済年金と厚生年金の一元化」によって、メリット部分が大幅に縮小され、徐々にサラリーマンの年金制度にサヤ寄せしていきます。
そうなってくるとやはり老後が気になります。今回はそんな公務員の老後の年金(退職金)としても活用できる個人型確定拠出年金(iDeCo)に加入するメリットとデメリット・注意点についてまとめていきます。
2017年1月から公務員も個人型確定拠出年金に入れる
2016年12月までは自営業者(第1号被保険者)や企業年金の無いサラリーマンしか加入することができなかった個人型確定拠出年金ですが、2017年1月より対象が大幅に拡大され、ほぼすべての人が加入できるようになります。
もちろん、公務員も例外ではなく、加入対象となります。
[bloglink url=”https://money-lifehack.com/insurance/4772″]
公務員が確定拠出年金に加入するメリット
個人型確定拠出年金に公務員が加入するメリットは年金の掛け金が全額所得控除、さらに運用益等も非課税になるなど税効果が高いです。
公務員という安定した身分を考えると、月々の家計収支のコントロールさえできれば上手に活用していきたい制度といえます。公務員の方も積極的に加入するべきです。
なお、確定拠出年金全般に関するメリットやデメリットについては「個人型確定拠出年金(iDeCo)のメリット・デメリット」でも紹介しています。
掛け金上限が低いため、固定手数料が相対的に高くつく
一方で公務員の方が注意すべきポイントは掛け金上限額の低さです。
公務員の方は月額12,000円までしか掛金を拠出できません。年間で144,000円ですね。
掛金が少ないときの注意点としては残高がなかなか増えません。残高が低いと問題になるのが手数料の存在です。
個人型確定拠出年金は利用に以下の3つの手数料がかかります
- 国民基金連合会への手数料:103円
- 事務委託先金融機関(信託銀行手数料):64円
- 運営管理機関(証券会社等):0円~475円
合計:167円~642円(年間と2,004円~7,704円)
上記の手数料が「定額」で発生します。定額の手数料は預けている残高が大きくなれば相対的に小さくなりますが、預けている残高が低いうちは相対的に大きいです。
残高が少ないうちは手数料率が5%を超えることも……
仮に上限金額を拠出したとしましょう。このときの初年度の掛け金合計の144,000円に対しての手数料率は1.39%~5.35%にも上ります。
現在の市場状況で5%を超える利回りを安定的に稼ぐのは難しいということを考えると、残高が少ないうちは手数料を含めて考えるとトータルリターン(利回り)がマイナスとなる可能性があります。
もっとも、この手数料は確定拠出年金の残高が増えていけばどんどん下がっていきます。
| 年金残高 | 手数料率(最小) | 手数料率(最大) | |
| 1年目 | 144000 | 1.39% | 5.35% |
| 2年目 | 288000 | 0.70% | 2.68% |
| 3年目 | 432000 | 0.46% | 1.78% |
| 4年目 | 576000 | 0.35% | 1.34% |
| 5年目 | 720000 | 0.28% | 1.07% |
| 6年目 | 864000 | 0.23% | 0.89% |
| 7年目 | 1008000 | 0.20% | 0.76% |
| 8年目 | 1152000 | 0.17% | 0.67% |
| 9年目 | 1296000 | 0.15% | 0.59% |
| 10年目 | 1440000 | 0.14% | 0.54% |
| 11年目 | 1584000 | 0.13% | 0.49% |
| 12年目 | 1728000 | 0.12% | 0.45% |
| 13年目 | 1872000 | 0.11% | 0.41% |
| 14年目 | 2016000 | 0.10% | 0.38% |
| 15年目 | 2160000 | 0.09% | 0.36% |
| 16年目 | 2304000 | 0.09% | 0.33% |
| 17年目 | 2448000 | 0.08% | 0.31% |
| 18年目 | 2592000 | 0.08% | 0.30% |
※年間の総積立金額に対する定額手数料を比率にしたもの。最小は月額167円、最大は月額642円を年額換算で計算。
掛金上限が小さい公務員の方こそ、手数料にこだわった確定拠出年金を
公務員の方にとっても個人型確定拠出年金は所得控除や老後の年金などを考えたら積極的に活用したい制度です。特に、従来までの公務員が優遇されていた年金制度がなくなったことを受け、お上だよりの老後は厳しくなっていく可能性が高いです。
自分自身での備えも必要になります。
一方で、前述のように、個人型確定拠出年金に係る手数料は毎月167円~642円です。
当然ですが、手数料は安いほうがいいに決まっています。
特に、公務員の場合は毎月の積立可能額が小さいため、定額手数料の影響を大きく受けることになります。
なお、手数料を下げる方法は金融機関によって手数料に差がある「運営管理機関手数料」を下げることです。
2017年現在では、SBI証券と楽天証券の2つの証券会社がこの手数料を無料にしています。今のところ、この二つの証券会社以外を選択するメリットがないような状況になっています。
なお、個人型確定拠出年金について詳しくは以下の記事でも証券会社(運営管理機関)について比較しておりますのでこちらも参考にしていただければ幸いです。
[bloglink url=”https://money-lifehack.com/asset-management/5790″]
以上、公務員が個人型確定拠出年金(iDeCo)に加入するメリット、デメリットをまとめてみました。
今、一番おすすめのモバイル回線は「楽天モバイル」です。
今は『楽天モバイル』が最強。楽天リンクを使えば通話かけ放題だし、パケットも使い放題で月々3,168円。データ通信をあんまり使わない人は1,078円で回線を維持できます。
さらに、家族と一緒なら110円OFF。
今なら三木谷社長からの特別リンクから回線を作ると、他社からMNPで14,000ポイント。新規契約なら11,000ポイントもらえるぶっ壊れキャンペーン中。