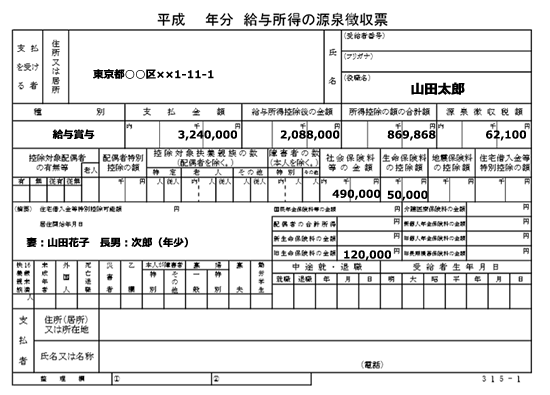年金収入1000万円超が増税へ。退職金の受け取り方(一時金・年金)にも影響
 2018年の税制改正によって、所得税の控除がみなおされます。2020年1月からは会社員の給料にかかる給与所得控除と同様に年金受給者が利用できる公的年金等控除が10万円減額されます。
2018年の税制改正によって、所得税の控除がみなおされます。2020年1月からは会社員の給料にかかる給与所得控除と同様に年金受給者が利用できる公的年金等控除が10万円減額されます。
その一方で、すべての納税者が利用できる基礎控除が10万円増額となるので、プラマイゼロなのですが、同時に、公的年金等控除に上限が付くことになるため、年金収入が1000万円を超える人にとっては増税となります。
今回はそんな年金に対する増税についての影響を見ていきましょう。
年金収入が年1000万円以上の人が増税になる
2018年の税制改正(実施は2020年1月より)については年収850万円以上のサラリーマンのケースが大きく取り上げられていますが、実は年金所得者にも影響があります。
[bloglink url=”https://money-lifehack.com/tax/income/14157″]
年収1000万円以上の年金収入者への税金が増税となります。公的年金等控除は年金収入金額に応じて決まっており、2018年現在では収入が増えると控除額も青天井で増額していきます。これに対いて、上限を1000万円とし、年金収入が1000万円をこえると、195.5万円で控除額が頭打ちになるという仕組みになります。
このため、年金等の収入が年1000万円を超えた方は増税となります。
年金収入で1000万円を超えるような人ってどれくらいいるの?
その一方で、年金収入が1000万円というのはかなりの高額です。給料収入であっても年収1000万円を超える人というのは4%弱とされているのに、年金でそれを超える人ってどれくらいいるのでしょうか?
たとえば、厚生年金+基礎年金についての保険料を“上限額”で払い続けたとしても公的年金の収入は400万円程度になると試算されます。公的年金は繰り下げ受給をすることで、現状では最大42%の増額が可能ですが、それでも600万円に届きません。
[bloglink url=”https://money-lifehack.com/insurance/3027″]
企業年金や確定拠出年金などが含まれると1000万円に到達する人も?
いわゆる公的年金だけでは年収1000万円に到達するのは難しく、実際には企業年金や確定拠出年金などの他の年金によって達成する人はいると思われます。
- 企業年金(確定給付年金)
- 厚生年金基金
- 企業型確定拠出年金
[bloglink url=”https://money-lifehack.com/working/7067″]
こうした福利厚生が充実した会社で、長年勤務した場合は月30万円ほどの企業年金を受け取っているような方もいるため、公的年金と合わせて受給すれば1000万円を超えるケースも出てくるでしょう。
企業によるものではなく、個人で備えることができる個人型確定拠出年金(iDeCo)も同様です。こちらも年金方式で受け取る場合は年金収入になります。
[bloglink url=”https://money-lifehack.com/asset-management/1348″]
退職金の受け取り方にも影響する?
多くの企業の退職金や年金の受け取りには退職所得扱いとなる“一時金方式”と年金所得扱いとなる“年金方式”を選択できるケースが多いです。
年金収入に対する増税の影響を受ける人であれば、この受給方法の選択についても影響を与えるケースが出てきそうです。
一方で、今回の改正による影響(年金収入1000万円超)というのは、財務省によると全国に3000人程度とごくごく少数ですのであまり大きな影響はありません。
給与所得控除同様に公的年金等控除も徐々に切り下がる可能性大
一方で、今後を考えると自分は関係ないと楽観視はできないと思います
この道はサラリーマンの給与所得控除が通ってきた道だからです。かつては給与所得控除も公的年金等控除と同様に青天井の控除でした。ところが、2013年に給与所得控除に“上限”が設けられ、なし崩し的に上限は年々下がっています。
[bloglink url=”https://money-lifehack.com/diary/13604″]
- 2013年:給与所得控除に上限(1500万円超に245万円固定)
- 2016年:同上限を引き下げ(1200万円超は230万円固定)
- 2017年:同上限を引き下げ(1000万円超は220万円固定)
- 2020年:同上限を引き下げ+一律10万削減(850万円超は195万円固定)
当初は年収1500万円以上という、だれが見ても高年収のサラリーマンが対象でしたが、2020年はそれが850万円というちょっと平均よりも稼いでいるサラリーマンで上限を迎えるようになります。
今後、同じように公的年金等控除についても縮小が続けば、定年時の退職金や年金の受け取り方への影響はもちろん、老後の働き方へも影響する可能性が高いといえそうです。
今、一番おすすめのモバイル回線は「楽天モバイル」です。
今は『楽天モバイル』が最強。楽天リンクを使えば通話かけ放題だし、パケットも使い放題で月々3,168円。データ通信をあんまり使わない人は1,078円で回線を維持できます。
さらに、家族と一緒なら110円OFF。
今なら三木谷社長からの特別リンクから回線を作ると、他社からMNPで14,000ポイント。新規契約なら11,000ポイントもらえるぶっ壊れキャンペーン中。