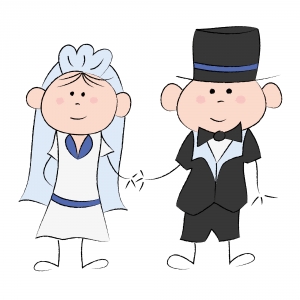相続税対策で暦年贈与(年110万円贈与)を行うときの注意点
 相続税対策の一つとして、年間に110万円までの贈与なら非課税にできる暦年贈与の仕組みがよく利用されます。
相続税対策の一つとして、年間に110万円までの贈与なら非課税にできる暦年贈与の仕組みがよく利用されます。
暦年(1月1日~12月31日)ごとの贈与が年間110万円以下であれば贈与税がかからない制度です。相続税対策における贈与というのはこの暦年贈与のことを指すケースが多いですね。
ただ、年110万円は非課税という内容だけが独り歩きして、相続税対策で贈与していたつもりが、後日税務署から否認されては大変です。
今回は相続税対策として暦年贈与を行うときの注意点を紹介していきます。
相続税対策で暦年贈与が認められない2つのケース
一般的な年110万円までの贈与をくりかえして相続財産をあっしゅくするという手法でよくあるミスというか、暦年贈与が認められないケースが2つあります。
一つが「名義預金」でもう一つが「連年贈与」です。
適当に相続対策をしてしまって、後日税務署から指摘されて贈与と認められなかったり、逆に多額の贈与が一度に行われたとして贈与税の申告漏れを指摘されたりしては元も子もありません。
名義預金は実質的な管理がモノを言う
被相続人(相続財産を持っている人)が相続税対策として配偶者や子供や孫の通帳に贈与分のお金を振り込みをするというケースがあります。
この時にありがちなケースとして、「通帳を被相続人が実質的に管理している」という場合があります。
たとえば、子ども名義の通帳を自分が持っていて、そこに振込なり入金なりで贈与分を預金していくというものです。
この場合、子ども名義の預金は「贈与されたことにならない」という判断されます。預金が「名義預金」と判断されます。
[bloglink url=”https://money-lifehack.com/tax/1906″]
つまり、名義は子供や孫であったとしても、その預金通帳を自身(被相続人)が借りしているのであれば、その預金は自身のものであると判断されてしまうわけです。
なので、振込(贈与)をする際は、その預金口座が相続人(子供や孫)が自由に使える口座である必要があります。
最初から贈与するつもりだった?連年贈与に注意
もう一つは、暦年贈与を何年も繰り返して行った場合、そもそもある決まった金額を贈与するつもりだったんじゃないの?と言われてしまうことです。
毎年110万円を10年間贈与した場合、これは110万円を10年間贈与したのではなく、「1100万円の贈与を10年間に分割して行った」とみなされることがあります。
これを暦年贈与ではなく「連年贈与」と言います。国税庁のタックスアンサー(よくある質問)に回答があります。
定期金給付契約に基づくものではなく、毎年贈与契約を結び、それに基づき毎年贈与が行われ、各年の受贈額が110万円以下の基礎控除額以下である場合には、贈与税がかかりませんので申告は必要ありません。
ただし、毎年100万円ずつ10年間にわたって贈与を受けることが、贈与者との間で契約(約束)されている場合には、契約をした年に、定期金給付契約に基づく定期金に関する権利(10年間にわたり100万円ずつの給付を受ける契約に係る権利)の贈与を受けたものとして贈与税がかかります。
ここにある通り、毎年110万円の贈与が個別に実施されていれば問題ないのですが、そもそも1100万円を贈与する予定であった場合は、最初の年に1100万円の贈与があったものとして課税される恐れがあります。
- 贈与の都度、贈与契約書を作成する
- 贈与の時期をずらす
- 贈与の金額をずらす
このような方法が挙げられます。
暦年贈与信託という方法もある
こうした暦年贈与と認められないリスクを排除する方法として信託銀行が提供している「暦年贈与信託」という信託商品を使う方法もあります。
信託銀行を利用して、贈与を行うことで契約回りなどもサポートしてくれます。管理報酬は無料となっており、まとまった相続財産があり、暦年贈与で相続財産を減らしていきたいという方にとっては有利なサービスといえそうです。
[bloglink url=”https://money-lifehack.com/bank/2528″]
また、相続税対策については暦年贈与以外にもいろいろな生前贈与での対応が可能です。詳しくは以下の記事も参考にしてみてください。
[bloglink url=”https://money-lifehack.com/tax/1932″]
免責・注意事項
こちらで書かれている内容はあくまでも一般論です。個別の事案についても税理士などの専門家から助言・アドバイスをいただくことを強く推奨いたします。
税理士に相談したい方は「税理士ドットコム」で税理士を探すことができます。
以上、相続税対策で暦年贈与(年110万円贈与)を行うときの注意点をまとめました。
今、一番おすすめのモバイル回線は「楽天モバイル」です。
今は『楽天モバイル』が最強。楽天リンクを使えば通話かけ放題だし、パケットも使い放題で月々3,168円。データ通信をあんまり使わない人は1,078円で回線を維持できます。
さらに、家族と一緒なら110円OFF。
今なら三木谷社長からの特別リンクから回線を作ると、他社からMNPで14,000ポイント。新規契約なら11,000ポイントもらえるぶっ壊れキャンペーン中。