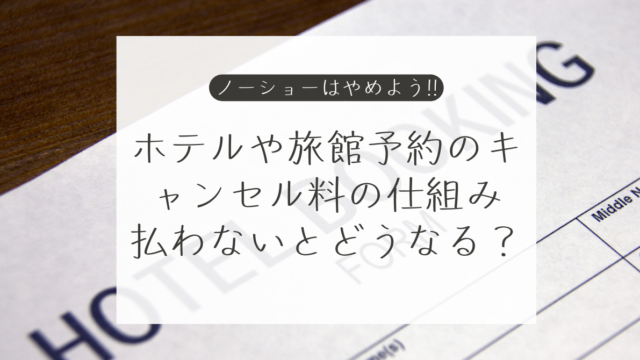儲けるの語源とは?お金を稼ぐ、お金を儲けるの違い
 お金を「儲ける」という言葉。「何かによってお金(大金)を得る」という意味で使われることが多いですよね。
お金を「儲ける」という言葉。「何かによってお金(大金)を得る」という意味で使われることが多いですよね。
そんな、儲けるという言葉は信じる者と書くように人を信じさせる(信者ビジネス)が重要、あるいはこの方法を信じて実行する人がお金を稼げるんです。というように使われる方がいらっしゃいますね。ただ、実際にはこの儲けるという言葉は「信者」ではありません。
今回はそんな儲けるの語源やなんとなく意味が似ているお金を「稼ぐ」という言葉との意味の違いについて紹介していきます。
儲けるの語源は「信+者(×)」で「人+諸(〇)」
お金を儲けるには人を信じさせる(騙す)ことなんだというのは、テレビかドラマかで使われたブラックジョークです。本来は「信+者」ではありません。「人+諸」が正しいです。
諸(ショ・もろ、もろもろ、これ)という言葉です。この言葉には意味がたくさんありますが、「たくわえる」という意味がります。それに人偏が加わるわけなので、もともとも意味としては「たくさん蓄えている人」という意味になります。
実際に中国語で「儲」という字は貯めるという意味で使われており、中国人に対して「お金を儲ける」という言葉を使うと、「貯金する」というような意味にとらえます。
そういったところで、儲けたいなら「人を信じさせなさい(信者を増やしなさい)」というのは、それが正しいかどうかは別として「儲ける」という文字の語源とは関係がないわけです。
日本で使われている「儲ける」のイメージは違う?
儲けるという言葉の語源については「蓄える」ということであるとしても、日本で「お金儲け」という言葉を使う場合は、どちらかというと「お金を得る」という言葉の上に「楽をして、濡れ手に粟で、手間をかけずに、思いがけずに」といったような意味合いが枕詞的にのっかっているように感じますね。
お金を儲けるとお金を稼ぐの違い
一方で、儲けると同じようにお金を得るという意味で使われる言葉に「稼ぐ(かせぐ)」という言葉があります。簡潔に言うと「お金を得る」という儲けると同じような意味の言葉です。
「稼ぐ」という文字を分解すると「禾(のぎへん)」+「家」の組み合わせとなります。禾は「穀物(あわ、稲)」という意味で使われますので、家に米を持ってくる、お米を収穫してくるという意味があるように考えられます。
働いてお金(穀物)を手に入れるという意味であって、こちらについては納得いただける方も多いのではないでしょうか。
儲けるという言葉に「楽をして」とか「思いがけず」といった意味があるのに対して、稼ぐという言葉には「自分自身が働いて」あるいは「積極的に動きかけて」お金を得るという意味合いがありそうです。
言葉の違いは重要ではないけれども
「儲ける」「稼ぐ」という言葉について、どちらもお金を得るという意味で使われることが多いです。
その意味で言葉を使うとき、儲けるを使うべきか、それとも稼ぐを使うべきなのでしょうか?この辺りは、個々人の感覚によるところも大きいとは思いますが、TPOに合わせて使い分ければいいと思います。
私個人としては、どこにフォーカスをするかで使い分けをしています。
- 結果か過程か?
- ミクロかマクロか?
まず、仕事による利益という結果を考える場合は「儲かる、儲からない」という言葉を使います。一方で、その仕事する過程そのものを指すと金は「稼ぐ」という言葉を使うことが多いです。
続いて、ビジネスの規模がミクロ的かマクロ的でも使い分けます。働き方や社内のオペレーションに関する部分では「稼ぐ」という言葉を使いますし、ビジネスそのものやマーケット(市場)単位でみる時は、儲かるビジネス、儲かるマーケットといったように使います。
あくまでも「私は」という話ですが、儲かる・稼ぐという言葉の使い方について紹介してみました。
※今回の記事は読者様からの質問に回答する形での記事投稿としております。
今、一番おすすめのモバイル回線は「楽天モバイル」です。
今は『楽天モバイル』が最強。楽天リンクを使えば通話かけ放題だし、パケットも使い放題で月々3,168円。データ通信をあんまり使わない人は1,078円で回線を維持できます。
さらに、家族と一緒なら110円OFF。
今なら三木谷社長からの特別リンクから回線を作ると、他社からMNPで14,000ポイント。新規契約なら11,000ポイントもらえるぶっ壊れキャンペーン中。