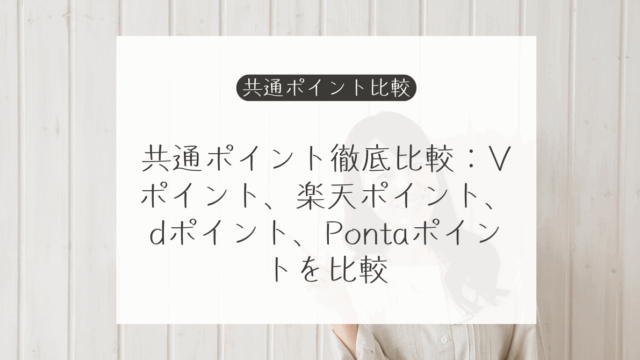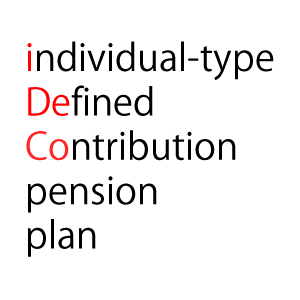2019年10月からの保育・幼児教育の無償化の仕組み
 2019年10月より就学前教育(保育・幼児教育)の無償化が実施されることになりました。
2019年10月より就学前教育(保育・幼児教育)の無償化が実施されることになりました。
子育てには本当にお金がかかりますよね。保育園や幼稚園の時期は公立小学校よりもはるかに高い保育料がかかります。そんな中で保育や幼児教育の無償化は前々より議論されてきた内容です。
2019年10月から全面実施となるにあたって、制度の趣旨や無償化の対象者や所得制限などのルールについてまとめていきます。
幼児教育の無償化の経緯
幼児教育の無償化については政府でもその重要性を訴え、年々議論されていました。
本格運用は2020年4月を予定していましたが、2019年4月に一部開始で2019年10月に全面運用するように前倒しがされました。これは2019年10月に予定されている消費税増税(8%→10%)に対する子育て世帯の負担軽減策としての意味合いもあるのだろうと思われます。
[bloglink url=”https://money-lifehack.com/diary/11971″]
これによって保育園、幼稚園、認定こども園などで行われる幼児教育を望めば誰もが経済的な負担なく得られるようになります。
幼児教育の無償化の対象となる人は?全員対象?
幼児教育の無償化ということは、すべての人が無償で保育園や幼稚園に子供を入園させることができるということになるのでしょうか?
まず、一つ目として「保育の必要性の認定事由に該当する/該当しない」という考え方があります。
保育の必要性の認定事由とは?
共働き家庭、シングルマザー(シングルファザー)の世帯は保育の必要性があると判断されます。一方で専業主婦(夫)家庭などについては、認定事由に該当しないと判断されます。
この認められる条件は自治体による判断となります。共働きだけどパート労働であるというような場合は、所得の状況や就労条件などをみて総合的に判断されることになります。
就労については月48時間以上でも認められるといった内容が報道されていますので、この保育の認定については比較的緩やかなものになるのではないかと考えられています。
子供の年齢と幼児教育無償化の種類・範囲
子供の年齢に加えて、保育の必要性認定の有無で無償化の内容は変わってきます。詳しくまとめたものは下記の表のとおりです。
| 保育の必要性の認定あり | 認定無し | |
|---|---|---|
| 0歳、1歳、2歳(未満児) | 無償化対象(住民税非課税世帯) 認可外は最大42,000円まで |
無償化対象外 |
| 3歳、4歳、5歳(未就学児童) | 無償化対象(所得制限なし) ・保育園 ・認定こども園 ・幼稚園(上限2.57万円) ・認可外保育施設(上限3.7万円) ※幼稚園の預かり保育を利用する場合、合計で37,000円まで |
無償化対象(所得制限なし) ・認定こども園 ・幼稚園(上限2.57万円) ※預かり保育は無償化対象外 |
0歳、1歳、2歳の未満児は保育の必要がある住民税非課税世帯のみ対象
未就園児の保育については年収要件があります。共働きなどで保育の必要性が認定された家庭であり、かつ住民税非課税世帯の場合、無償化の対象となります。
[bloglink url=”https://money-lifehack.com/tax/10488″]
条件を満たしている場合、認可保育園や認定こども園を利用する場合は無償化の対象。認可外施設を利用して保育サービスを受ける場合は最大42,000円まで補助されることになります。
3歳、4歳、5歳の未就学児童は制限なしで全員無償化
3歳以上の園児・児童に対しては年収や家庭環境に関係なく、無償化の対象となります。ただし、表にしている通り、保育の必要の有無によって、無償化の範囲が異なります。
<保育の必要性が認定>
認可施設(保育園、幼稚園、認定こども園)のいずれも無償化の対象です。ただし、幼稚園については通常保育料金は月額2.57万円までで、預かり保育の保育料も含めて月額3.7万円まで無償化対象です。
認可外の保育施設やベビーシッター等を利用する場合も37,000円までと上限付きで補助されます。これは全国の認可保育所の平均保育料を上限にしたものです。複数の施設やサービスすを使った場合でも上限範囲内なら補助を受けられます。
<保育の必要性が認定されず>
認定こども園や幼稚園のみ無償化の対象となります。幼稚園の場合は保育料月額2.57万円までが無償化のはんいないとなります。預かり保育については無償化対象外となります。
また認可外の施設は補助の対象外です。
幼児教育無償化は家庭にとっては朗報
2019年10月から全面的に施行される幼児教育の無償化は幼児を抱えている多くの仮定にとっては負担軽減の朗報となるでしょう。
気になる部分は「保育の必要性が認定」というところですかね。これが実際にどのように運用されるのかで、夫婦の働き方などに影響を与える可能性がありますね。
※こちらの記事は2018年8月22日時点で公開されている情報、報道されている情報を元に執筆しております。情報が新しくなりましたら随時アップデートしていく予定です。
今、一番おすすめのモバイル回線は「楽天モバイル」です。
今は『楽天モバイル』が最強。楽天リンクを使えば通話かけ放題だし、パケットも使い放題で月々3,168円。データ通信をあんまり使わない人は1,078円で回線を維持できます。
さらに、家族と一緒なら110円OFF。
今なら三木谷社長からの特別リンクから回線を作ると、他社からMNPで14,000ポイント。新規契約なら11,000ポイントもらえるぶっ壊れキャンペーン中。